「レルネット主幹」 三宅善信 「四十にして惑わず」いうまでもなく、『論語』為政編にある有名なことばである。全文は、「子曰、吾十有五而志乎學、三十而立、四十而不惑、五十而知天命、六十而耳順、七十而従心所欲、不踰矩」という短い文章であり、高校の「漢文」の時間で習うので、ほとんどの日本人が耳にしていることばである。60歳の「還暦」や70歳の「古稀」同様、40歳のことを「不惑」と呼ぶことも、広く定着している。 私事になるが、私はこの7月27日で、満40歳を迎えた。私がこの言葉を学校で習った当時(たぶん15歳頃だったと思う)、「15歳から勉強を始めたのでは遅すぎるな」(当時の私は「學」と「勉強」の区別がついていなかった)と漫然と思ったものである。それにしても、「三十にして立つ」は、なんとなく解るものの、「四十にして惑わず」と「五十にして天命を知る」は、当時の私としては少し理解がしがたかった。ただ、「六十にして耳に順(したが)う…」や「七十にして心の欲するところに従えども、矩を踰えず」に関しては、要するに、歳を取って人の言うことを許容できなくなったので「さすがの孔子も老人ボケしたかな」と思ったことを鮮明に覚えている。 その時に考えたのが、「人間の総合能力40歳最高説」である。右の図表を見て欲しい。現代の日本人の平均年齢は約80歳であるので、私が80歳まで生きられたとして(もちろん、交通事故で明日にも死ぬかもしれないが、一応、人並みに長生きできたとして)、体力面では、恐らく20歳前後がピークだったと思う。このことは、特別に体力を使う仕事に従事している人は別として、普通の人ならほとんど変わらないであろう。体力に関しては、あとは下降してゆくのみである。 一方、人生上のさまざまな経験およびそれに基づく判断力については、年齢が増すほど増えてゆくのも事実であろう。ただ、ここで注意しなければならないことは、理屈の上では、長生きすればするほど経験の量は増えるのであるが、実際には、加齢に伴い、記憶力が低下することによって、せっかくの経験も「忘れ」られてゆくのが一般的である。しかも、世の中に「変化」というものがなければ、これもそれなりの意味があるのであろうが、実際には世の中は急激に変化しており、「昨日の常識が明日の非常識」になることはよくある。このような場合、このような場合、過去の成功体験がかえって邪魔になって、変革のタイミングを逃すということが度々起こりうるのは、昨今の、日本の政治・経済状況を見るまでもなく明らかである。最近、「老害」という言葉が各分野で聞かれるのは、このことであろう。 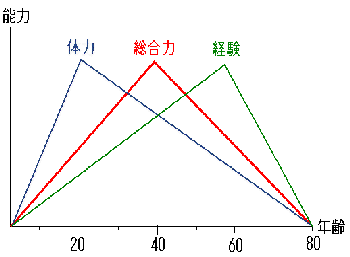 そうすると、人生の道のりの中で、どの時期が一番充実しているかという問いには、体力と判断力の総合として、40歳前後と答えずにはおれまいと思う。ところが、わが国の多くの組織では、トップが60代(場合によっては70代、宗教界なんか80以上の場合もある)である。このことは、すなわち、人間としての総合力からいうと、街角にたむろしている茶髪のティーンエージャーに大組織の舵取りを任せているのと同じくらい危険なことである。一般的な会社でいうと、40歳の課長が一番総合的な「能力」があって、50歳の部長は30歳の係長と能力的にはほぼ同じ。60歳前の常務はぺーぺーの新入社員と変わらないということである。ほとんどの人は気づかないかもしれないが、たとえば、10歳にもなって「おしっこたれ」をしていたら叱られるが、1歳2歳なら叱られないであろう。同様に80歳にもなれば、「失禁」しても、叱る人はいないであろう。躾(社会生活への適応)のもっとも基本的な要素である「尿意のコントロール」ですらできなくなるのであるということは、80歳を越えると、ある
意味で「赤子同然(プリミティブな状態)」ということである。だから、「早く40歳(最高の状態)になりたい」と、二十年以上も前に思ったものである。 そうすると、人生の道のりの中で、どの時期が一番充実しているかという問いには、体力と判断力の総合として、40歳前後と答えずにはおれまいと思う。ところが、わが国の多くの組織では、トップが60代(場合によっては70代、宗教界なんか80以上の場合もある)である。このことは、すなわち、人間としての総合力からいうと、街角にたむろしている茶髪のティーンエージャーに大組織の舵取りを任せているのと同じくらい危険なことである。一般的な会社でいうと、40歳の課長が一番総合的な「能力」があって、50歳の部長は30歳の係長と能力的にはほぼ同じ。60歳前の常務はぺーぺーの新入社員と変わらないということである。ほとんどの人は気づかないかもしれないが、たとえば、10歳にもなって「おしっこたれ」をしていたら叱られるが、1歳2歳なら叱られないであろう。同様に80歳にもなれば、「失禁」しても、叱る人はいないであろう。躾(社会生活への適応)のもっとも基本的な要素である「尿意のコントロール」ですらできなくなるのであるということは、80歳を越えると、ある
意味で「赤子同然(プリミティブな状態)」ということである。だから、「早く40歳(最高の状態)になりたい」と、二十年以上も前に思ったものである。ここまで言っても「40歳頃がトップだなんて信じられない」と言う向きもあるであろうから、別の角度から論証しよう。子供の頃に観た『ベンハー』や『クレオパトラ』といった往年の大スペクタル映画のシーンで、古代ローマの「元老院」の場面が出てくるが、トーガという半肩を露出したような独特のローブを着けた「元老院」の議員たちがみな、筋肉モリモリであったのが不思議であった。当時の私には「元老」という言葉のイメージに引っ張られて「地位の高い(老)人による議会」というイメージがなんとなくあったからである。しかし、実際に歴史で学んでみると、ほとんどの「元老院」の議員は、30歳代であった。それなら、筋肉モリモリも不思議ではない。同様に、わが国の時代劇の「老中」や「若年寄」といった幕府の執政職(現在でいうところの閣僚ポスト)も、この「老」とか「年寄」という字に騙されていたが、たいていの場合、30歳代でその任に就くようだ。そして、40代半ばには、家督を嫡子(たぶん20代)に譲って「隠居」の身となる。維新の功労者や明治の元勲といわれるような人たちもたいてい30歳代で国政のトップの位置に立った。つまり、40歳で一国や組織のトップに立っても なんら問題はないはずである。現に、クリントン大統領は40代の前半で世界最強の国のトップに立ったし、マイクロソフト社のビル・ゲイツもしかりである。これらの人物が、どこかの国や会社の60代70代のトップのようと比べて、能力が劣ると思えない。 しかし、現在の日本で、30代で制度的に「年寄」と呼ばれるのは、角界(大相撲)くらいのものだ。15歳くらいから初めて、30歳頃に「現役を引退」し、「年寄○○」を襲名するのが一般的だ。「相撲は体力勝負だから30歳で引退も当たり前だ」と反論される向きには、最も頭脳を使う仕事である「プロ棋士」の世界をみれば納得してもらえるであろう。囲碁や将棋の棋士は、一日中、盤の前に座っている仕事だから、飛んだり跳ねたりといった意味での「体力」は、ほとんど要らないであろう。ところが、羽生善治4冠王や佐藤康光名人といった最強の棋士はみな20代半ばである。谷川浩司竜王まで拡げても30代半ばまである。かつての名人たちである中原誠永世十段や米長邦雄九段・加藤一二三九段など50歳代の棋士には、ほとんど輝きがない。つまり、制度によって保護された社会的な地位や組織のごときものを全く取り払って「一個の人間」として勝負すれば、そのピークは40歳よりも前にあることはあっても、後ろにあることはないということである。 そもそも、「生物としてのヒト」(縄文人や現在でもアフリカや南米のジャングルに棲んでいる「プリミティブ」な人々)の平均寿命は40歳前後と推定されている。ヒトが80年も生きられるようになったのは、ここ百年くらいの間の急激な食料の増加や医療の進歩のおかげである。もし、ヒトがその天寿のとおり40歳前後で死ぬとすれば、入れ歯も老眼鏡も補聴器も要らないであろう。脳卒中や癌や心筋梗塞にもほとんどならない(成人病に罹る前に死ぬから)。考えてみるまでもなく、生物が生きている目的は、子孫(=遺伝子)を遺すことであるから、鳥類や哺乳類は、昆虫や魚類のように卵を生みっぱなし(すなわち、性的成熟と寿命とがほぼ同じ)という訳にはゆかないが、子供を育てる(つまり、子供が次の世代の子供を作れるようになるまで育てる)という戦略を取っているにしても、性的能力の喪失(更年期)以後は、生物的に言えば、生きている意味がほとんどない。 そこで、最初の問いに戻るが、「四十にして惑わず」とは、何を意味するのであろうか? すなわち、「人間として、これより先、自己の能力がアップするということはあり得ないので、いろいろと自己の可能性について惑わず、ひとつの方向に絞れ=他の可能性は諦めよ」ということである。当然、「五十にして天命を知る」は、「先(自己の限界)が見えた」ということである。ついでに、「六十にして耳に従う」は、「人の言うことが聞けなくなる」ということであり、「七十にして心に欲するところに従えども、矩(のり)を踰(こ)えず」というのは、「ボケが始まった」ということの含蓄のある言い回しである。 古代インドの思想に、人生の「四住期」というものがある。すなわち、最初は、一人前になるためにいろいろと学ぶ期間である「学生(がくしょう)期」。次に、一家の主として妻子を養い、社会的な仕事をなす期間である「家住(かじゅう)期」。それから(ここからが、きわめてインド的なのであるが)、出家して精神的な修行生活に入る「林住(りんじゅう)期」。そして最後に、それら一切を越えた境地である「遊行(ゆぎょう)期」の、人生における4つの節目である。この考え方から言っても、もし人生を80年とすると、だいたい20歳頃までが学生期、40歳頃までが家住期、60歳頃までが林住期、そこから先が遊行期ということになろう。 一年程前、私は妻に「私は、もうそろそろ林住期に入るから、これからは妻子のことは気にかけず、私個人のスピリテュアルな世界に入る」と言ったら、「不摂生が祟って、とうとう成人病にでもなったんですか? だって臨終期なんでしょう」と言われてしまった。「りんじゅう」違いもはなはだしい。「終わりに臨むの臨終ではなくって、林に住むの林住だ」と言ったら、今度は、「キャンプにでも行くのですか?」と言われた。知らぬほど強いものはない。 人間としての総合力は既にピークを迎えた私であるが、幸いこれから先の20年間は、経験や判断力といったスピリテュアルな面がさらに充実できるはずであるから、他人の言うことに耳を貸さず(己の「耳に従う」)、典型的な徘徊ボケ老人(己の「心に欲するところに従え」)であるところの「遊行期」めざして、人生の道のりを進めたいと思う。「老人は赤子と同じ」あるいは「縄文人や現在でもアフリカや南米のジャングルに棲んでいるプリミティブな人々」といった、一見「差別的」とも取れる刺激的な表現をしたが、逆に「プリミティブこそプライマリーなり」であって、成長=社会適応によって後天的にドンドンと身につけていった「余計なモノ」をドンドンと削ぎ落として行って、最後に残るモノこそ私自身のプライマリー(本質的)なものである。と、満40歳の朝日(雨が降っているにもかかわらず、日の出が拝めた)を観つつ思った。 |