レルネット主幹 三宅善信
▼公私の区別は足許でする
明治維新以来、既に130年以上が経過し、この国における欧化は、あらゆる分野で浸透しているように見える。あるいは太平洋戦争の敗戦後急激に拡大した米化も、すでに半世紀以上に及び、この国のあらゆる面において欧米化が進んだように見える。街を行き交う人々で和服姿(着物・帯・下駄・草履といったようなものをひっくるめてという意味で)の人を見かけることは、何かのイベント(成人式や卒業式等)でもない限り、ほとんどなくなった。日本人のほとんど100パーセントが、洋服に靴姿である。そもそも、洋服という言葉が死語になっているくらい、単に「服」といえば、和服ではなく洋服を指すようにすらなっている。服装の問題はそれほど重要なテーマたり得るのであるか、今回はこの履き物の着脱に焦点を当てて、日本の文化について、考えてみたい。
明治以来、公的な場所は全て土足(靴を履いているという意味)になった。役所、学校、駅、病院、ホテルこれらの施設は全て、明治時代から土足である。現在では、会社をはじめ不特定多数の人が集まる場所で、土足でない場所を探すことのほうが難しい(註:そういう意味でもお寺の本堂は特別な存在である)くらい、靴を履いた社会生活というのが、日本人の日常生活に浸透している。これほどの短期間に、生活の様式をすっかりと欧米化させた国というのは少ないであろう。もちろん、現在では、どの国に行っても、自動車もあればテレビもある。しかし、アラブ圏やインド圏の人々の姿を思い起こして欲しい。日常の服装にしても、あるいは社会生活においても、日本のように姿形だけをそっくり真似て(もちろん、中身は別物である)、そのまま欧米スタイルをスタンダード化している国はむしろ少ないと言える。
しかし、それではすっかり日本人が西洋化してしまったのかというと、そうとは言えない。なぜなら、先ほどの西洋化した生活――特に「靴を履く」という意味で西洋化した生活――様式は、あくまで日本人のパブリックな場所における行動パターンに限られるからである。一方、プライベートな生活の場である家庭に入ると、一概に状況はすっかり変わる。明治以来130年間以上、日本人は公的な生活空間において靴を履いてきた(土足)が、一歩プライベートな生活空間に入ると、話はまったく別である。個人の家屋の中でまで、靴を履いたままで入る人というのは、まず99パーセントいないであろう。依然として日本人の私的な生活空間では、素足(スリッパや靴下を履いているとしても、いわゆる外の道で履く靴は履いていない)なのである。テーブルや椅子といったすっかり西洋化した家具を使って生活をしているのにも関わらずである。
確かに、ここ20年くらいの傾向として、マンションなどを中心に、伝統的な畳敷きの部屋(註:床の間、押入、仏壇等を含む)の多くが個人の住宅から消え、フローリングが一般的になってきたが、これとて、そもそも、日本の家屋において部屋中に畳を敷きつめるようになったのは、安土桃山時代における大名屋敷あたりからの伝統である。庶民の家屋に畳を敷きつめるようになったのは、近世の江戸時代に入ってからのことである。それより以前は、『源氏物語絵巻』などを見ても解るように、日本の家屋はそもそも床板張り、すなわちフローリングだったのである。寝所には、いわばベッドのような形で、そこにだけ畳が敷かれていたり、座る場所にだけ、臨時に何か移動可能なゴザのような敷物(註:それ故に、「たたむ」という動詞から「たたみ」という名前が付けられた)が敷かれていたのである。したがって、フローリングの流行というのは、ある意味で伝統的な日本の家屋の様式に先祖帰りしたと言ってもよいのである。しかし、このような日本家屋の建築様式の変化の長い歴史を経て、なんら厳然してと変わらないのが「玄関で靴を脱ぐ」という行為であり、おそらくこの様式は今から百年経っても、この国においては変わらないであろう。そこで、玄関というスペースに焦点を当てて考察を進めてみたい。
▼内から外と外から内
ほとんどの日本家屋において、わずか畳半畳分のスペースしかない「玄関」は、大きな意味を持った空間である(註:他に畳半畳分のスペースで大きな意味を持っているのは「墓」であるが、本件については、別の機会に譲る)。特に、扉の問題がある。もちろん、伝統的な日本家屋における玄関扉は、西洋式のドアではなく、ガラガラッと横に開ける引き違いの扉であった。現在でも、窓や障子といった建具のほとんどは引き違いである。広い解放空間を確保しながら、なおかつ、扉そのものが一元的(直線的)に運動することによって使えなくなるスペースというものを最小限に押えた(註:一次元は面積を持たない)引き違い形式であるが、玄関のドアだけは、ほとんどの家が一見、欧米のドアと同じような形のいわゆる押し引き(push
/ pull)形式のドアという形(註:二次元的に扉面状に動くドアは空間(玄関土間)を大きく(約8割)占有する。(90X90)―(1/4XπX90X90)=0.785)になってしまった。これには、マンションなどの集合住宅の普及や、都市における犯罪の増加による防犯上の理由ということもあって、施錠が容易な洋風のドアが一般家庭においても普及した。ところが、実は一見洋風のドアに見える玄関が、欧米と日本のそれとでは、決定的に異なる点があるのである。
皆さんも想像して欲しい。日本家屋における玄関ドアは、ほとんど100パーセント「内から外」に向かって開く。一方、欧米の家屋の玄関ドアは、ほとんど「外から内」に向かって開かれるのである。もちろん、欧米でも、比較的狭いスペースに不特定多数の人が集まる映画館や劇場等の施設においては、消防法の規定により、何かの事故が起った時に、大勢の人が一度に外へ逃げられ易いように、外開きのドアが設置されている場所がないわけではない。しかし、一般家屋の玄関ドアにおいては、ほとんど全て内側に開き、いわばその家への訪問者を迎え入れるという形態を取るのである。
一方、現在の日本の家屋における玄関ドアは、先ほど述べたように、ほとんど外向きに開く。なぜなら、日本では、例外なく個人の家の中では靴を脱ぐからである。たいていの玄関は、畳半畳くらいのスペースしか確保されていないであろうから、ほとんど、同じ回転半径(扇面状の移動スペース。占有率約80%)を有するドアが、もし内側に開いてきたとしたら、脱いだ靴に当ってしまう。したがって、日本家屋の玄関ドアが外向きに開かなければならないというのは、家の中では靴を脱ぐという日本人の生活文化上の必然なのである。しかも、このことは、ドアの外側で待つ人が、内側からいきなりドアを開けられることによって、扉で顔面を打つという危険があるので、扉の回転半径分以上の間隔を扉から離れて、その家の主によってドアを開けてもらうのを待たなければならない。しかし、これは、日本で他人の家を訪問した時のことを考えれば、ドアを開けてもらって最初にする行為がお辞儀を含んだ挨拶であるから、両者が頭を下げてお辞儀をし合っても、ぶつからないために必要な合理的距離とも言える。
▼招かれざる客
握手もしくは抱擁が基本的な挨拶である欧米においては、日本における両者のドアを挟んだ距離よりも、初対面時のお互いの距離が小さくなければならない。したがって、招き入れる様式のドアのほうが合理性がある。そもそも、握手という挨拶方法は、自分の素手を相手に見せることによって、武器を所持していない(あなたを害しようという気持ちがない)ということを表現するための挨拶法として確立されたのである。
それでは、玄関のドアが、内開きと外開きのどちらのほうが外敵の侵入を防ぐのに都合が良いか考えてみる。先ほどは、客を招く場合であったが、外敵から身を守るという場合を考えてみよう。相手が無理やりドアを力ずくで押し破ってくるということを考えた場合、一見、外開きのドアのほうが突破されにくいように思うが、それは大きな間違いである。よほどのバカではない限り、ドアの取っ手を捻って、扉を開けて入ってくるのであるから、突進する牛馬のように、無理やり力ずくでドアを押して入ってくるなどということは、あり得ない。日本式(外開き)の場合、もし、外敵が力ずくでドアを開けようとする場合、扉と挟んで両者が取っ手を掴み、外敵はドアを外に引っ張って開けようとし、逆に家屋内にいる人は、開けられまいとして、内側にこれを引っ張るという漫画のような形が取られる。
欧米の場合はまったく逆である。日本のドアでも、鍵が開けられないという前提に立てば、外開きも内開きも保安上あまり関係ないように思われるが、もし、相手によって鍵が破られた場合を考えると、実は内開きのドアのほうが外敵の侵入を防ぎやすいのである。皆さんも、ハリウッド映画やアメリカのテレビドラマなどのシーンを思い浮かべて欲しい。得体の知れない外敵の侵入を防ごうとする時に、よく、ドアの内側に家具を立て掛けたりして、これを防ごうとしているシーンが描かれているであろう。そうなのである。ドアが内開きの場合は、ドアの内側に家具などを適切に配置すると、相手がたとえ鍵を壊したとしても、力ずくでドアを開けることは物理的に不可能なのである。一方、日本のように外開きのドアであれば、家具を立て掛けても無駄である。したがって、内開きのドアというのは、侵入者を防ぐという意味も持っているのである。日本でも、防衛的な目的で造られた城郭や、域内が治外法権的意味(不入の権)を有する大寺院等の城門や山門では、閂(かんぬき)を掛けて閉める形式の両開きの西洋式のドア形式(引き開き)が用いられている。
▼素足になったという仲間意識
さて、日本の玄関ドアの直後にあるわずか90センチ四方(畳半畳分)のスペースで「靴を脱ぐ(上がる)」という行為は、実はわれわれが考えているよりもはるかに大きな心理的バリアを、その地点を通過することによって、人々に与えているのである。なぜなら、一旦、家の中に靴を脱いで上がった以上、その家の人(と同様)と見なされ、そこから逃げ出そうと思しても、もし靴を隠されでもしたら裸足で逃げなくてはならなくなる(註:屋内とは逆に、裸足で外を歩く人は変人と見なされる)からである。よく、政治家同士の会合(裏取引)や同業者同士の談合が、彼らの本来の「職場」である議会や会社等の公的施設で行われずに、「料亭」などの「靴を脱いで上がる」私的施設で行われるのは、そこに居合わせた列席者一同に「一蓮托生」を意識させるための儀礼の場として必要だからである。単に公費(機密費や接待費等)による飲み食いが目的なら、個室のある一流レストランでも高級クラブでも十分なはずであるが、それでは、この「儀礼」を終えたことにならないことになるからである。
本論の冒頭で、「明治以来、日本のパブリックな空間においては、原則として土足ということが守られてきた」と述べたが、唯一そうでない空間がある。それは、お寺の本堂などの宗教施設である。昨今では、生活の洋風化に伴い、正座が苦手な人が増えて、お寺でも椅子席のところもたくさんあるが、それでも、ほとんどの寺院は、やはり靴を脱いで本堂に上がる形式である。このことは、法事に参列する人々(親族)や法要に参拝する人々(檀家)に対して、靴を脱がすことによって、擬似的な家庭的一体感というものを感じさせ、なおかつ、瞬時に「その集団から抜けられない」ということを、暗示するさせる装置なのである。同じ宗教儀礼でも、誰でも参列できる葬儀や、不特定多数の住民(氏子)が参加する神社の祭りなどは、たいてい「土足」で行われる。
数年前、大きな社会的問題となった「法の華三法行」事件(『宗教と詐欺の境界線をご一読いただければ判るように、その「天声」等のバカバカしい教義については、あまりにお粗末すぎて、まったく関心がなかったが…。)で、ただひとつ私が感心したのは、この宗教の教祖が、信者の足の裏を観てそれぞれの人の運勢を分析し、それぞれに対して教えを諭した(註:被害者=元信者から言うと「騙された」のであるが、この部分が、「根拠のない霊視商法だ」と批判する論議には、私はまったく関心がない)という方法(=足裏診断)である。正直、私は「うまいところに目を付けたものだ」と思った。足の裏で運勢が判るなどとは微塵も思わないが、その教祖に会って運勢(足の裏)を観てもらうためには、まず、靴を脱いでその宗教の施設に入らなければならない。その時点で既に、精神的にその教祖のほうが優位に立っているのである。足の裏を見られるということは、日本人の集合無意識から言えば、既に、潜在的にその集団から「内の論理」に絡み捕られてしまって、外に逃げ出せなくなっているのである。
▼シークレットサービスの大失態
話は変わるが、わが三宅家には、結構、外国からの賓客が来ることがる。今から11年前の4月に、元アメリカ合衆国大統領のジミー・カーター氏という超大物(註:その翌々週には、スリランカのジャヤワルデネ前大統領夫妻も来られた)が、大阪のわが家を訪れられたことがある(註:三宅家訪問のためだけに来日されたので、日本滞在はわずか24時間だけだった)。この時、諸々の打ち合わせの交渉係を担当した私は、非常に面白い体験をした。当時は、湾岸戦争の直後ということもあり、日米共に警備が厳重を極めていた。面白いことに、アメリカ合衆国の大統領というのは、たとえ大統領職を辞した後でも、亡くなるまで一生シークレット・サービスが身辺を警護するのである。当然のことながら、前大統領や元大統領であっても、軍事上の最高機密を数多く知っているので、もし、彼が誘拐でもされたら、国家安全保障上、大変なことにからである。
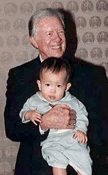
カーター氏に抱っこしてもらう三宅代表の長男(当時1歳) |
カーター元大統領がわが家に来られた時も、1週間以上も前から、シークレット・サービスの先遣隊が下見に来て、(銃撃などに耐えられるように)壁の厚さが充分あるかや、万が一襲われた時は、反対側から逃げられるように、通路やドアが2ヵ所以上確保されているかなど、念入りに調べて行った。そして、カーター氏夫妻が来られた当日、私は玄関先でシークレット・サービスのエージェントにこう言った。「日本の家屋では、靴を脱がなければならないので、下足袋を持ってウロウロしたのでは仕事にならないでしょうから、脱いだ靴は私共で預かりましょうか?」と聞いたのである。それに対してエージェント氏はこう言った。「No
thank you. I can manage」と…。そこで、わが方では、カーター氏とロザリン夫人の靴だけを預かり、元大統領夫妻を家族を挙げて歓待したのである。

カーター夫妻と三宅ファミリーの夕食会での記念写真 |
わが家で半日過ごされた元大統領夫妻が、夕食を終えて、いざ、お帰りになられる段になって、思わぬトラブルが発生したのである。車寄せのある玄関で、大統領夫妻をお送りしようとした時、シークレット・サービスの人たちが「靴がない」と言い出したのである。わが家には玄関が複数あり、必ずしも入っていただいた入口から出ていただくとは限らない。だから、「こちらで靴を預かりましょうか?」と、エージェント氏に尋ねたのである。しかし、彼らは、もし他人に靴を預けてしまったら、いざというとき、自分たちの動きが十分とれないと思っていたのであろう。おそらく、家の中でも、常に靴を履いていることを前提に生活している彼らにとって、靴を脱ぐということ、そして、またその靴を履き直さなければ外に出られないということが、来日するに当たって、理屈の上では理解できていても、感覚的には消化できていなかったのであろう。大統領夫妻を見送った時(玄関先には、数多くのご近所の人々が見物に集まっていた)、シークレット・サ−ビスの連中は、わが家の迷路のような廊下を走って、反対側の玄関まで自分の靴を探しに行き、結果的には、ほんの2〜3分間のことではあるが、警備陣がまったくいないという空白の時間帯が生じたのである。もちろん、何も事件が起らなかったから良かったようなものの、この時、私は日米のある意味での文化の違いを実感した。
玄関のドア板一枚を隔てて、家の内と外では、日本人お得意の「ウチの論理・ソトの論理」といった、いわゆる二重標準が厳然としてあり、あるいは、上足(素足)と下足(靴履き)とを使い分けることによって、いわゆる「浄・不浄」という意識の区別が生じるのである(註:要点は、靴を脱ぐか脱がないかというところにあり、下足の状態のままで「門」を通貨するだけでは、たとえ敷地内であったとしても、あまり「ウチ」という意識が働かないのかもしれない)。これらは、日本文化を理解する上で大変重要なキー概念であるので、いずれまた講を改めて論じることがあるかと思うが、このわずか厚さ数センチの玄関ドアを隔てて、世界観、あるいは行動規準がまったく激変するというのが、日本文化を理解する上で重要な通過儀礼装置なのである。