レルネット主幹 三宅善信
▼『消費者契約法』って何?
2001年4月に『消費者契約法』が施行されて2年と3ヵ月が経過した。この法律は、事業者と消費者との間の契約において、一般に「弱者」とされる消費者に、不当な不利益が生じないことを目的として定められたものである。戦後(戦前も同様であった)のわが国の急激な経済発展は、とりもなおさず、消費者よりも生産者・事業者の利益を重んじて、「集約化」や「効率化」を進めてきたことによって成し遂げられたということは、否定できない事実である。しかし、十年以上続く平成大不況の真っ只中にあるとはいえ、依然としてアメリカに次ぐ世界第二の経済大国である日本においては、一応は、その物質的繁栄が達成されて(註:生産の大規模化・効率化は、恒常的に需要を上回る生産の過剰をもたらし、さらにはアジアの途上国の追い上げもあって、余剰産物の輸出の伸びも期待できず、慢性的なデフレ傾向を招いた)しまったので、これ以上の経済成長の見込めなくなった社会の目標も、生産者重視から消費者重視へと大きく舵が切られることになったのは必然のなりゆきであった。
この動きは、今回、取り上げる『消費者契約法』に先立って、1995年に施行された『製造物責任法(通称:PL法)』に続く一連の法体系変更の一貫である。『PL法』は、文字通り、事業者によって大量生産された商品の扱いに伴う事故で被害を受けた者に対して、従前は、実害を受けた消費者の側が、裁判の過程において事故の再現実験等の実証責任義務(註:設備や専門的知識のない一般消費者には、ほとんど不可能である)を嫁していたものを、逆に、訴えられた企業側に、反証実験を通して自己の無過失性を証明させるように条件を変えたことによって、この問題に対するスタンスの大きな転換が行なわれたのである。そこからさらに敷衍して、今回は、工業製品等(ハード)だけではなく、製造物といったような具体的な形を伴わないサービス等(ソフト)に対しても、社会的に「弱者」(註:個々の案件については、たしかに個々の消費者は弱者かもしれないが、こと立法に関しては、有権者の多数を占める消費者のほうが強者である)とされる個々の消費者と、「強者」とされる企業(もしくは団体等)間で、「弱者である消費者を保護し、事業者と個々の消費者との力関係の差によって不当な契約が結ばれていないかどうか」ということを問題にした法律である。
私は、このような法律体系を整備して行くこと自体は、資本主義市民社会が成熟していく上で、大いに結構なことであると思うが、この法律を取り巻く昨今の風潮は、およそサービスの「消費」と思えないことにまで、この法律を逆手に取って、具体的には、「消費者契約の解除に伴うトラブル」についての訴訟を起す傾向があることを憂うものである。日弁連などの解釈によると、「金銭等の授受を伴う行為は、すべて売買契約である」というふうに認定しており、あたかも、通信販売で現物を見ずに購入した物品が実際に手元に届いた時に、その広告内容と実物が大きく異なっていたりした時に、「消費者が商品を気に入らずに返却した場合は、2週間以内であれば、事業者はクーリングオフ(註:契約の解消と購入代金の返却)に応じなければならない」といったようなものと同次元で、なんでも解決できるとしている傾向があるが、私はそのことに同意できかねる。
▼日本文化的「消費」の意味
私は今回、私立大学に対する「入学金返還訴訟」を題材に取り上げて、この問題について考えてみたい。というのも、以前から本件を採り上げようと思っていた矢先に、本日、京都地裁において、全国初(註:同様の裁判が各地で争われている)の「入学金返還訴訟」が、予想通り、被告である「大学側の全面的敗訴」という判決を招いたからである。なぜ「予想通り」と言ったかというと、今回の判決を下した京都地裁の判事も、本件を大きく「好意的に」採り上げたマスコミも、また、「敗訴した大学側(弁護団)」自身すら、本件の持つ「日本文化論的意味合い」の深さをまったく理解していないからである。
その前に、まず、そもそも「消費とは、いったいいかなることか?」という概念規定から話を始めなければなるまい。「消費」についての私の意見は、2000年1月に上梓した『速佐須良比賣(はやさすらひめ)のお仕事』で述べたように、「物事が完全に費えて消えるということは、物理的にはありえないことである。むしろ、経済行為における消費とは、その経済的付加価値が減少するという意味である」というように概念規定した。卑近な例で申し訳ないが、消費とは「ビールを飲んだ後で小便をするようなもの」である。ビールも小便も茶色い泡だった液体であるが、ビールには商品としての付加価値があり、小便は排泄物として付加価値がないのである。しかし、液体の量としては同じだけある。決して費えて消えるということはない。ただ、ビールが人体を通過する間に変質(経済的付加価値の減少)するだけである。これが、経済的な意味での「消費」である。
さて、今回、取り上げる問題は以下のようなケースである。大学受験において(註:大学受験に限ることはないが、論旨を判りやすくするために、本論では大学受験の場合を例にあげて考察を進める)ある受験生が複数の私立大学を受験して、そのうちのいくつかの大学に合格した学生が、「実際には、入学しなかった大学に対して、支払った入学金や前期授業料等を返還しろ」という訴えである。なぜなら、実際にその受験生はその大学に行かなかったのであるから、これは、いわば「消費契約の解除」に当たり、入学金や授業料は大学教育というサービスへの対価として支払われるべきものであるので、具体的なサービスを受けなかった以上、サービスの対価としての入学金や授業料を大学側が返還するのが当然である。というのがこの訴訟の主旨である。
▼前納金はボッタクリか?
話を判りやすくするために、ある単純なケースを想定してみよう。ある受験生が、偏差値の高い順からA大学、B大学、C大学の3つの私立大学を受験した。それぞれの大学の入学金はいずれも50万円ずつであり、初年度の授業料は前期50万円+後期50万円の合計年100万円である。一般的に、偏差値の低い(人気のない)大学から順に入学試験が実施されることになっている(註:当然のことながら、偏差値の高い大学の合格発表が先にあれば、良い大学に受かってしまった者は、それより偏差値の低い大学をもう受験しないだろうから、一般的に言って、偏差値の低い大学ほど先に入学試験を行ない、早く合格者を出して学生を確保しようとするのは経営上、当然の行為である)。もちろんのことながら、この受験生の第1志望は、最も偏差値の高いA大学であった。けれども、彼の実力ではB大学はなんとか合格できるだろうが、A大学となると、よほど「山」でも当てないかぎり難しいと思われていた。しかし、試験当日の体調不良など不測の事態に備えて、いわゆる「滑り止め」として、さらに偏差値の低いC大学を受験したとする。もちろん、入学試験ならびに合格発表は、C大学、B大学、A大学の順で行なわれた。
彼はまず、C大学に合格し、50万円の入学金と前期授業料50万円の合計100万円を納入金の〆切り日までに納めた。それから数日して、B大学の合格発表があり、実力どおりB大学にも合格したので、彼はB大学に入学金の50万円と前期授業料の50万円の合わせて100万円を納付した。続いて合格発表のあったA大学には、やはり、残念ながら不合格だったので、当然のことながら、彼は、4月からは、晴れてB大学の学生となったのである。ただし、そこで彼は思った。滑り止めで受けただけのC大学には、実際に全く通学していないのに、支払った入学金と前期授業料の合わせて100万円が惜しくなって、「これをなんとか返還してほしい」とC大学に申し込んだが、当然のことながら、C大学の窓口は、「入試要項にも書いてあるとおり、『一旦、納入されたお金は、いかなる理由があっても返却いたしません』あなたも、それを承知の上で、当大学を受験され、そして入学金等を納入されたのではないですか。実際に当大学への入学を辞退されたのは、あなたの恣意的な行為ですから……」という官僚的な答弁で、ケンもホロロに追い返された。彼は思った。これではまるで「ボッタクリ」じゃないか……。
確かに、大多数の受験生たちは、この入学金前納制度のことは、苦々しいとは思いながら、ほとんどの私立大学がカルテルでも結んでいるかのように、この制度を採用しているために、受験するときには一応、「保険」と思って、無駄金になるかもしれないことを納得して受験したはずである。そこで彼は、ある弁護士事務所を訪れ、同じような立場の元受験生たちと謀って、C大学に対して入学金返還集団訴訟を起したのである。これが今回のテストケースであるが、実際このような裁判が、全国の数十の私立大学を相手に起され、現在、係争中なのである。
▼キャンセル料という考え方
日本における私立大学の経済的基盤は、主に以下の4つの柱から成り立っている。ひとつは、実際に在籍している学生からの授業料等の納付金。2つめは、入学希望者による入学金等の前納金。3つめは、大学が独自に行った収益事業や任意の寄付、あるいは基本財産からの利子収入等である。そして、4つめが、国からの私学助成金という名の国庫補助金である。当然、国庫からの私学助成金については、受験生とは関係ないので、今回は考察対象から除外する。また、実際に通学している大学教育の受益者である学生が払う授業料についても、その金額の多寡は別として、支払うこと自体に疑問抱く人はほとんどいないだろう。問題は、任意の寄付、特に入学希望者からと、合格者による入学金の2項目である。個人からの任意の寄付については、わが国の社会風土上、裏口入学等の疑惑を招くケースが多いので、できればなるべく避けたいと思っている社会的合意がある。しかも、わが国の場合、欧米のように、公益法人に対する第3者による善意の寄付がほとんどの場合は税控除されないので、寄付の金額はたかがしれている(註:アメリカの大学などでは、個人名でも遺産金などから億単位の寄付が行なわれ、個人名を冠した講座や、立派な校舎や図書館がいくつも建っているのが一般的である)。
そして、今回問題になっている「合格者による入学金」である。現状では、日本の私学の経営は、完全にこの収入を計算に入れて成り立っている。もし、実際には大学に来ない合格者(別の大学に行った人)による入学金がすべて返還されなければならないのであれば、実際にその大学に来ている学生の授業料は大幅に値上げされてしまうことになってしまい、おそらく相当な金持ちの子弟でなければ私学に通うことができないことになるであろう。これこそ、ある意味での「社会的不平等」を生むことになる。つまり、これはある意味、社会保険等と同じ概念で、一人の病気なった人の医療費を多くの健康な人が担うことになる社会的分担に近い考え方とも言える。実際に通っている学生の授業料を実際に通っていない人々が少しづつ担っているのである。それ自体、受け入れられない制度ではない。ただし、合格したがその大学に行かなかった受験生からすればなにか、釈然としないものがある。
一方、大学側の論理は、ホテルや航空券の「キャンセル保障金」に近いものであろう。つまり、予約を入れていた客が、当日になって急にキャンセルした場合、実際には、そのホテルを利用しなかったにもかかわらず、「泊まったのと同じ額を請求する」ということである。当然のことながら、ホテル側は、予約をしていた客のために、必ず部屋を確保しておかなければならず、後から申し込みのあった客に、「あいにくその日は満室でございます」と言って、断っていたかも知れないのであるから、当然、当日になってキャンセルされたホテル側の遺失利益は大きい。そこで、ホテル業界などでは、前日までにキャンセルした場合、1週間前までにキャンセルした場合、1カ月前までにキャンセルした場合等と、細かく定款を決めて、それぞれのキャンセル料を徴収することが一般になっている。
航空券の予約についても同じことが言える。この3月末に、私は健康上の理由で、オックスフォードへの出張を2日前になってキャンセルした。当然のことながら、航空券を手配した旅行代理店に対しては、キャンセル料として航空運賃の25%を支払った。航空会社も、私のために確保しておいた良い席が、2日前になってから売れるという可能性はほとんどない(註:実際に2日間でその席が売れることもあるだろうが、売れたからといって私にキャンセル料を返す必要はない)ので、いわば「空気を運んだだけ」ということになり、私は航空会社に対して損害を与えたのであるから、実際には乗らなかった飛行機のためのキャンセル料を支払ったのである。
▼一生使えるブランドの名義使用料
こういう考え方からすると、入学金を支払った学生が来なかった大学としては、この学生のために定員枠を1人分使ったのであるから、その見込みが不意になったので、当然「キャンセル料を取ってもいい」という考えになる。私学の経営者にとって、毎年、合格者の何パーセントの学生が入学辞退をするかを読む(これを「歩留まり率」と呼ぶ)かが、その年の学校経営にとってたいへん重要である。はたして、入学金不返還という考え方は、大学側の主張するようなホテルの宿泊予約の「キャンセル料」のようなものなのであろうか? しかし、「入学金返還訴訟」における原告(受験生)側の主張では、「入学金および授業料はいわば、各授業毎の"チケット制"が一般的である英会話スクールや自動車教習所と同じように考え、実際に大学で受けた授業に相当する金額のみを支払えばよいのであって、入学辞退によって実際に授業を受けていないのであれば、サービスの対価としての入学金や授業料は返還されて当然だ」と考えるのである。
しかし、よく考えてみれば、いわゆる「滑り止め」にされた大学はこけにされたわけであり、そもそも5校も10校もの大学を受験して、なおかつ合格したいくつかの大学に入学金を前納できた学生は、それだけの経済的余裕があったのであるから、所得税の世界における累進税と同じ考え方で、その学生(たいていの場合は学生の親権者が払う場合が多いが)が収める入学金は、社会的公平の視点から言っても、無駄になっても問題はないと思われる。世の中には、経済的余裕がないために、「滑り止め」の措置をせずに、本命一本で勝負した学生もたくさんいるのであるから、「滑り止め」の大学をいわば「掛け捨ての保険料」としてヘッジすることのできた学生は、それだけ恵まれているとも言える。あるいは、男女間の恋愛関係で、二股をかけていたA男が、B子と結婚すると決めたので、これまでC子にプレゼントした物が惜しくなってプレゼントした商品を返して欲しい」というようなものである。こんな理屈が通るなら弄ばれたC子があまりにかわいそうである。
私はそもそも、私学教育というものを行政が提供する公教育を補完するための「民間による官業の依託」とは認識していない。したがって、私学においては公立学校における『学習指導要項』に準じたカリキュラムを組む必要すらないと思っている。しかも私学教育における入学金や授業料といったいわゆる「納付金」を、単なる「サービスの対価」とは考えていない。なぜなら、もしこれが授業という「サービスの対価」であるのならば、4年間の大学教育を終えた時点で、その人と大学との関係はなくなるはずである。しかし、多くの場合、就職活動のの際の履歴書や、お見合いの釣り書などには、必ず「○○大学卒」と書くではないか(註:これが自動車学校なら、履歴書には「普通自動車免許取得」としか書かないではないか? 決して「○○自動車教習所卒」とは書かない。逆に、大学の場合、「○○大学XX学部卒」と書いて、決して学校名ぬきで「XX学士」とは書かない)。したがって、わが国における大学教育は、「資格」ではなく、いわば、「一種のブランド」なのである。しかも、大学を卒業しても一生付いてまわるブランドなのであって、「良い学校」なら就職や結婚等にとっても有利であるし、あるいは就職してからでも、社内や役所の中には、歴然とした学閥というものがあって、その大学の卒業生であるということが、出世の原因になったりするのである。すなわち、一生「受益者」となれるのである。

エルメス家の御曹司Simon Xavier Gerund Hermes氏
とはNGO活動を通じて十数年来の仲である |
ということは、ある大学の卒業生は、そのあと何十年にもわたって、その大学の卒業生であるということから利益を受けているのであるが、授業料として払った金額は、たった4年間分であり、それこそ不当である。そのことから逆算すれば、
における納付金は、たとえ「授業料」という名前が付いていたとしても、それを単純には、大学における授業という「サービスの対価」とは言い切れないのではないだろうか? 実質1万円の鞄が、ヴィトンやエルメスのマークが付いているだけで10万、20万になるのと同じことであり、世の女性の多くはヴィトンやエルメスのマークのために10万、20万のお金を投じているのである。単なる物を収納するケースとしての鞄とは意味が異なるのである。大学も同じことである。
▼私学は塾であり、道場である
そもそも、わが国における「私学」というものは、近代社会が想定している「欧米的な大学」とは本質的に性質を異にしているのである。欧米の有名私立大学の多くは、各教会(church=教団)が聖職者を養成するための神学校を創ったことに端を発する場合が多い。教会という「価値を共有するコミュニティ」の継続的な発展をもたらすための先行投資として学校教育が行なわれたのであり、その証拠に、各大学共たいてい最も古い学部は神学部であり、続いて、法学部や医学部が整備されるようになり、総合的なuniversityに発展していった場合が多いが、わが国の近世における子女教育は、寺子屋を始めとした私塾(道場)からスタートしたケースがほとんどである。緒方洪庵の適塾(大阪大学の原形となった)や、地方でも吉田松陰の松下村塾を始め、数多くの私塾が存在し、江戸には門弟1万人を有するよう巨大な塾(道場)もあったそうだ。中には、石田梅岩の「石門心学」のように全国展開する塾もあった。
今でも、「慶應義塾大学」というふうに、「塾」という名が付いている大学もあるではないか。福沢諭吉を慕う青年、大隈重信を慕う青年、新島譲を慕う青年、それぞれがいわば、師匠の「内弟子」として、塾生(門下生)になったのであり、これがわが国における近代私立学校の原形である。近代国家の官僚を作るために創れた国立大学(帝国大学)とは、根本的に異なる。そこにおいては、教える者と学ぶものとの関係は、いわば「師匠と弟子」の関係であり、この「師弟関係」は、現在でも医学部において顕著に見られる。有名な大学の医学部を卒業した学生が、その大学の系列の病院に就職したり、あるいは、東大、京大、阪大、慶應といった特定の有名医学部OBが教授陣の大半を占める地方の医科大学もたくさんあり、いわば、完全に系列子会社化してる地方大学や病院はいくつでもある。その意味で、わが国における医学教育は、極めて前近代的な徒弟制度の下に行なわれている場合がほとんどである(註:もちろん、善し悪しの両面があるが、この「系列の壁」が、医療事故が起こった際に、ミスを起した医師や体制を糾弾しにくい温床となっているのである)。
私塾はまた「道場」という呼ばれ方もした。明治15年(1882年)に、「柔道」を創始した嘉納治五郎師範の「講道館」をはじめ、NHKの大河ドラマ『武蔵〜Musashi〜』でもお馴染みの剣術指南の「吉岡道場」などを見ても判るように、道場には、その道場の主宰者である道場主(師範)を頂点に、師範代以下、厳格なヒエラルキーが存在し、道場に入門する際には、たいていは、間に紹介人(保証人)を立てて申し込み、入門のための謝礼金を道場主に前払いするのは言うまでもなく、田舎から親族が出てきた時には特産物を道場主のところに持って行ったり、正規の稽古代の他にも、盆暮れの挨拶(中元・歳暮)を行なうのは半ば「常識」である。読者の中にも、いつもお世話になっているホームドクターに、中元や歳暮をしている人はかなりいると思われる。病気の診療・治療という医者としてのサービスへの対価としては、当然、その都度費用を払っているのであるから、それだけで十分なはずであるが、たいていの人は「お医者さんには、いつ世話になるか判らないから」ということがあるかないのか知らないが、この種の出費に及んでいるであろう。私も毎年、十数人に中元・歳暮を贈っているが、このうち実際に半年の間に「お世話」になる人は、まずいないどころか、実際に出会うことすら、ほとんどない人たちだが、恒常的に盆暮れの「付け届け」をしているし、また逆に、これらとは全く別の人たちから、同じくらいの中元・歳暮を頂戴している。
▼家元の三権
実は、これは日本文化の大きな特徴のひとつである「家元制度」と共通の根を有している現象なのである。茶道や華道はいうまでもなく、能・狂言・歌舞伎、囲碁・将棋等々……、わが国の伝統文化伝統芸能の多くは「家元制度」によって支えられてきた。それぞれの流派には「宗家」とか「宗匠」と呼ばれる家元がいて、流派毎に、世襲制である家元を頂点に厳格なヒエラルキーが構成されており、その「芸(技)を習う」ということは、すなわち、その人の「弟子になる」ことであり、入門後は、決められカリキュラムに従って(註:自分で工夫した「新しい技」を生み出すことは忌避され、何ごとも先例の「型どおり」に真似ることが、奨励されている)、徐々にステップアップ(註:いくら「実力」があっても、昇給は一段づつが原則である)していくのである。
家元制度を根幹をなす家元の特権は、大きく分けて3つある。まず、「免許を授与する権限」である。これには、必ずといってよいほど金銭の授受が伴う。このシステムが家元制度の経済を支えているのである。たとえば、わが国最大の茶道流派である裏千家今日庵においては、免許状だけで、入門・子習い・茶箱点・茶通点・唐物・台天目・盆点・和巾点・行之行台子・大円草・引次・真之行台子・大円真・正引次
という14段階のグレードがあり、それぞれの免許を申請する時に、所定の金額を収めなければならないのである。しかも、京都市上京区小川通にある裏千家今日庵で家元から直接手前を習う弟子はほとんど皆無に等しく、実際には、全国に点在する裏千家から「準教授」などの資格を付与された茶道教室の先生のところへ行って習い、そこから裏千家に対して免許状の申請をするのである。
例えば、「行之行台子(ぎょうのぎょうだいす)」という免許を取得するために、12,000円の費用がいるが、これはあくまで裏千家そのものに出す茗荷金(名籍料)のようなものであり、実際には、各地方の茶道教室の「先生」にも、それなりの「謝礼」を添えて、家元に取次いで頂くのが慣例となっている。これが、いわば家元の持つ「免許の発行権」である。
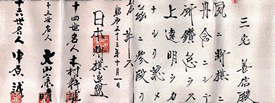
将棋も江戸時代は幕府から公認された
「名人」という家元制度に支えられていた。
四百年間に「(永世)名人」は17人しか存在しない。 |
2番目が、その「流派の統制権」である。先ほども指摘したとおり、伝統芸能というのは、芸を習おうとする人がそれぞれの個性を発揮して新しい何かを工夫するということは嫌われるのであり、先人がした通り、文字通り「習って」いくのが伝統芸能である。本来、「実力」が問われるべき武術においても同様であり、それ故、「師範」や「指南」と呼ばれるのである。そして、これらを評価し、体系化しているのが家元(総家)である。
家元の権能の3番目は、「破門権を有する」ということである。伝統芸能における「家元の権威」は絶対的であり、家元に「お前は破門だ!」と言われれば、それを仲裁してくれるような第三者、あるいは再審してくれるような公的機関はなく、いかに弟子のほうに正当な理由があったとしても、破門する権利は一方的に家元の側にあるのである。
これらの3つの機能を有しているのが家元制度であるが、実は、わが国における大学の制度もこれに近い。もちろん「免許の発行権」というのは、いわば、博士・修士・学士等の学位を授与する権利であり、「流派の統制権」というのは、学閥の人事権やシラバス等を作成したりする権利であり、「破門権」はもちろん、退(停)学処分を決定することができるということに対応しているのである。したがって、日本の私立大学というのは、たとえ名前が「大学」と付いていても、近代日本社会が頭だけで考えている欧米的な社会制度としての大学などでは決してなく、日本の伝統的な芸事の世界における「流派」として捉えるほうが適切であり、よって、大学を卒業してからも一生「○○大学のOBです」と言えるような、一種の擬似宗族社会が形成されるのである。
▼一子相伝という厳しい掟
私はよく国連関係の会議でニューヨークへ訪れるが、現地には「ニューヨーク三田会(慶應義塾大学の卒業者で、ニューヨークに支店のある銀行や商社等の有名企業に勤務する日本人社員からなるOB会で、しばしば、家族ぐるみ親睦のイベントが行なわれている)」というようなものが、それぞれ有名大学毎に存在するのである。ハーバード大学なんか、なんのかんのといって「税控除」付きの寄付金依頼書を送りつけてくるが、私も、日本におけるHarvard
Alumni/ae Society(同窓会)の幹事をしたことがあるが、ビジネスマンや官僚たちにとっては大変メリットのある団体と見えて、皆さん大変熱心に活動していた。
茶道や華道、能・狂言、歌舞伎等の伝統芸能における家元の権威を否定し、そのようなことにお金を払うのが嫌であれば、その人は自ら新流派を起せばいいのである。私の周りにも、自称"家元"が何人かいる。しかし、その流派を世間の人々が評価するかどうかは別の問題である。例えば、私が、濃茶・薄茶等の点前がものすごく巧くて、茶道の新流派「裏萬家」を興したとしても、おそらく弟子はほとんど集まらないであろう(註:現在の裏千家の家元は、私の大学の一年先輩であるが)。それが400年続く、千利休に始まる「千家」というブランドの力なるものである。「進歩的文化人」と呼ばれる人の中には、富と名誉を独占している封建的な家元制度に対してネガティブな感情を持っている多いらしいが、その人たちは、日本文化の本質の何たるかをご存じないのだろう。家元は、その富と名誉を独占するために、家元家の内部でもたいへんな研鑚が行なわれていることはあまり知られていない。
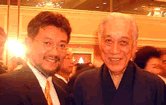
同志社大学の大先輩でもある
裏千家先代家元の千玄室大宗匠と |
例えば、表千家・裏千家・武者小路千家のいわゆる「三千家」においては、これら三千家だけが「千家」の名籍を独占し続けるために、たとえ家元の息子に生まれても、次男坊・三男坊は、独り立ちしたら――この場合の独り立ちとは、結婚して一家を起したらという意味――別の姓を名乗らなければならないという厳しい掟があるのである。本年2月、43歳の若さで逝去した現在の裏千家家元千宗室氏の実弟伊住政和氏も、結婚を機会に千家の姓を離れ、自ら新しく一家を起さなければならなかった。このように、家元家(狂言和泉流の和泉元哉氏の言葉を借りれば宗家家)は、その希少価値を保つために、自らの血を分けた兄弟すら排除し続けて「一子相伝」を保つという努力が代々積み重ねられてきたのである。
つまり、このような「家元制度」の中に、日本の伝統文化を引き継いだものとして、近代日本の「私学教育」というものが現実に存在にしているのである。したがって、再々言うように、大学の納付金というものは、実際に授業を受けたかどうかというような単純な「サービスの対価」として支払われるものでないのである。もし、この裁判の原告団が主張するように、「いったん収めた入学金でも、結局、本人がその学校に行かなくなったのだから返えせ」と言うのであれば、自分の親が死んで、代々の檀那寺に永代供養料を納めて納骨したが、その後、別の新宗教の信者になったので、いったん納めた永代供養料や茗荷金を寺に「返えしてくれ」というような無茶な話である。これこそ、日本の伝統文化、社会の公序良俗に対する謀反ではないだろうか。あるいは、最初に述べたように、二股でつきあっていた女と「別の女と結婚することにしたから、今までお前にやったプレゼントを返してほしい」というような話と同じことになってしまう。
そういえば、日本の大学がいかに「家元制度」的存在であるかを顕著に示すひとつの例を思い出した。社会一般の常識から考えれば、ある学生が授業料を払うのを中止し、退学届を大学に提出したら、それだけで退学できるかのように思われるが、手続き的には、その学生は大学側から「退学許可」をもらわなければならないのである。欧米的な近代法の概念から言えば、学生側が「私は○○大学の学生を辞めます」と公に宣言(註:大学当局への文書で通告)し、授業料を納入しなければ、自動的に「契約解除」とみなされて「退学」になるのであるが、日本の場合は、あくまで入退学を決めることができるのは、一般的に大学側にその主体があり、これはまさに家元制度がいうところの「破門権」と同じなのである。であるからして、大学の入学金返還訴訟における問題は、原告側(弁護団)が主張するような単なる「消費問題」としての経済行為、あるいは契約概念だけにこの問題を矮小化してはいけない日本文化に本質に関わる多くの問題が含まれているのである。