レルネット主幹 三宅善信 ▼アンゴルモア=モンゴル人? 1999年の7の月」もあと数日しか残っていないが、『ノストラダムスの大予言』をネタにバカ騒ぎした連中(出版・放送関係者、一部の終末論的教団)は、いったいどのような社会的責任を取るつもりなんだろうか? もともと、この国では、政治家やメディアに至るまで、「社会性」という感覚が欠如しているから、「責任」があることすら感じないのだろうから、責任の取りようがないのだろうけれども…。その辺のところを、『TIME』誌(Asia版)の7月5日号で特集("JAPAN: Apocalypse Soon?")していたが、本当に、世界中の物笑いである。 そもそも、「予言」などというバカげたことを口にするだけでも、その人物(作家・メディア・教団等)の程度が知れるというものだ。女子高生同士のトークならいざ知らず、このような戯言を公共の電波を用いて社会に垂れ流すことこそ犯罪的行為と言えよう。モロ出しヘアヌードをテレビで流すより悪質だ。私が郵政大臣なら、そのような放送をオンエアしただけで、その局の放送免許を没収してやる。小渕内閣のアイドル野田聖子大臣ならそんな蛮行はしないだろうが…。もっとも、予言という行為そのものを否定する発言ならいたしかたないが…。 私は、昨年9月10日付の本エッセイ『論理的にあり得ない「予言」:似非宗教に騙されないために』で、次のように述べた。「予言」や「占い」が成立する条件として、「事前に全てのことが決定され」ている必要がある。だからこそ、その「未来(来るべき将来)を観よう」という意欲が湧くというものだ。さもなければ、占うこと自身、意味がなくなる。しかしながら、これから先に起こることを100%の蓋然性をもってハッキリと予測することは、量子力学理論など持ち出すまでもなく、論理的には不可能なことである。ただ、将来の出来事に対して言えることは、確率論的な予測(例えば、サイコロを振って1の目が出る確率は6分の1である)のみである。 したがって、「占い」や「予言」の前提となっている「決定論」が成り立たない以上、いかなる「占い」や「予言」も成り立たないことは、自明の理のはずである。ノストラダムスを持ち出すまでもなく、星座、血液型、四柱推命、前世・来世、終末等々いかにこれらを巧妙に組み合わせようとも、すべて論理的には整合性を持たない。もし、あなたの周りにいる宗教家で、これらについてひとことでも触れる人がいるとしたら、その人はインチキだと考えて間違いない。「ノストラダムス教」の伝道師の中には、「恐怖の大王アンゴルモアは、モンゴル人のことだ」と解釈している連中がいると聞くが、私は、先日、そのモンゴルへ行ってきた。もちろん、当のモンゴル人たちはノストラダムスのことなんかほとんど誰も知らないが…。 ▼クーデター騒動を経験 私は、7月7日の晩から10日の早朝までの日程で、大阪国際宗教同志会の理事として、「十日ゑびす」で有名な今宮戎神社の津江明宏師と共にウランバートルを訪問した。モンゴル仏教総本山のガンダン寺院で、モンゴル仏教最高位のハンボ・ラマ(管長)チョイジャムツ猊下と会見したのをはじめ、同国大統領の諮問機関宗教評議会のダムバジャフ師と同国の宗教法人法制定等について会談。国立ウランバートル大学内の仏教学研究所の教授陣と仏典保存復刻事業について意見交換を行った。 私がモンゴルを訪れるのは、1986年、91年、94年に続いて4回目のことである。それぞれに深い思い出がある。まず、初めてモンゴルを訪問した86年は、モンゴルはまだ社会主義体制下であった。中ソ両国が国境線を接して軍事的に対峙した時期のソ連側からのいわば「緩衝地帯」のような場所がモンゴル(人民共和国)であった(中国側からの緩衝地帯は、内蒙古自治区)。当時、既に83歳であった祖父(三宅歳雄)と3兄弟揃って、はるばる北京から列車で片道32時間という気の遠くなるような旅行の末にやっと辿り着いた「草原の国」であった。モンゴル国内では、ものものしい戦車ややたら偉そうにしているソ連兵の姿が目に付いたのが印象的であった。 ウランバートルでの公式行事の合間を縫って、小型機をチャーターしてゴビ砂漠まで往き、ゲル(遊牧民の伝統的な円形の天幕)に一泊した。その晩に見た星空(「宇宙にはこんなにたくさんの星があるのか?」と思えるくらいの「満天の星」があり、とりわけ星々の密度が高い「天の川」の部分が本当に「Milky Way(銀河)」と呼べるほど白くハッキリと「川状」に見えた)が、その後、私をモンゴルに引きつけるひとつの要因になった。そのキャンプから何時間もジープを飛ばしてアルタイ山脈の麓まで行ったときは、千数百年前に、シルクロードをはるばると経典を求めて天竺(インド)まで行った「三蔵法師」玄奘のことを想起した。なぜなら、玄奘が国禁を犯して唐土から出国したのが28歳(629年、帰国は16年後)の時であったが、当時、私もちょうど28歳だったからである。 2度目の1991年は、兄と共に空路、北京からウランバートルに入りした。この北京首都空港で出発便を待つ間に、空港内の雰囲気が一変した。社会主義国の常ではあるが、何の説明もないまま、急に手荷物検査や人物検査が厳しくなり、空港ビル内に自武装した兵士の数が目に見えて増強された。やっとのことで搭乗口近くまで行くと、われわれの搭乗口の隣は、襟に金日成バッチを付けた北朝鮮の外交団と思しき一行が、持ちきれない程(大きさと個数が制限されているはずの機内持ち込み手荷物を一人当たり、大きなスーツケース3〜4個持参)の荷物を抱えて大慌てで平壌(ピョンヤン)往きの便に搭乗してきた。 何が起きたのか気になったが、知らされないままにウランバートル入りしたら、出迎えてくれたモンゴルの政府関係者が「ソ連でクーデターが起きた。詳しいことは判らない」とのことであった。北京空港での謎が解けたのはいいが、一瞬ぞっとした。というのも、この時は、モンゴル滞在に続いて、シベリアの中心都市イルクーツクとハバロフスクを訪問する予定だったからである。日本や欧米の国にいれば、世界中でどんな事件が発生してもほとんどリアルタイムでTV中継されるのであるが、元々、情報公開という概念が社会主義体制下の上に、ここシベリアはモスクワから遠く離れており、何がなんだかさっぱり判らない。結果としては、ソ連大統領のゴルバチョフ氏が失脚し、ロシア共和国大統領のエリツィン氏が権力を掌握するという歴史の転換期をロシアで体験することになった。 中でも、記憶に残った出来事は、ローカル鉄道(シベリア鉄道の支線)に、血相を変えた自称KGB関係者が乗り合わせ来て、「もし、(追っ手の)官憲に問われたら、『私と1週間ずっと一緒に鉄道で旅行していた』と言って欲しい。そうしたら、私のアリバイができるから…」という、まるでスパイ映画の1シーンを観るような出来事があった。ホテルで視たTVニュースも、放送局を乗っ取った側に有利な情報を流すが、直ぐにまた画面が切り替わって、反対側に有利な報道がなされるので、いよいよの時は、放送局のいうことを信じてはいけないといういい教訓になった。エリツィン側の勝利に終わったクーデターも、モスクワから遠く離れたイルクーツクでは、職場や軍隊内で日頃から気にくわなかった奴を、実際に何派であったかは関係なく「こいつはリガチョフ派だ」といって吊し上げ、追放してしまう市民裁判のような光景を何度も目撃した。 ▼隔世の感 3度目の1994年は、社会主義体制が崩壊してまだ日の浅い時期であった。そもそもが「遊牧民の国」という、社会主義の前提であるべき資本主義経済すら経験していなかったモンゴルが、東欧社会主義各国のドミノ的崩壊に連られて市場経済体制へと移行したが、元はといえば、草原と砂漠の広大な国土に人口わずか200万人というこの国では、まともな「資本市場」が育つはずもない。中露両大国の間に挟まれたこの国が、観光資源を活かして外貨を獲得しようにも、一年の大半が冬である寒冷地(最低気温は氷点下20度)では、観光事業も年間ほんの数十日程度しか見込めず、お先真っ暗に思えた。ちょうど、海部総理(当時)が日本の首脳としてはじめてモンゴルを公式訪問した時期と重なった。 この時には、面白いエピソードがあった。海部首相はモンゴルの地を踏む最初の日本首相として、政府専用機(ジャンボ機)に満載の援助物資を積んできたが、なにせあまりよく整備されていないウランバートルの空港で滑走路(舗装すら十分でなく、離発着の際には砂煙が巻きおこる)が短いため、専用機の機長が「荷物満載だとウランバートル空港の滑走路が短すぎて自身がない」と言ったので、せっかくの援助物資の半分を北京に積み残してきたそうである。国民の血税を何と考えているのであろうか? おまけに、数少ないウランバートル市内のドルショップ(外貨でしか買い物ができない高級品店)は、すべて海部首相ご一行様と同行のマスコミ関係者が大量に買い物をしてしまったのか、ほとんどスッカラカンであった。 そして、今回が4度目の訪蒙である。どういう訳か、今回もまた小渕総理の訪蒙と時期が重なった。初めてモンゴルを訪れた時には、北京からでも陸路32時間もかかったのに、今回は、関空から直行便でわずか4時間の空の旅である。あまりに簡単すぎて、「草原の国」に到着しても、有難味がないというものだ。しかも、最初の時は、一年間にモンゴルを訪れる日本人の総合計が外交官も含めて60人しかいなかったのに、私と同じエアバスに乗り合わせている日本人だけで200人以上はいる。モンゴルへ着いてからも、通訳案内をしてくれる女性にもひっきりなしに携帯電話がかかってくるし、会談したラマ教(モンゴル仏教)の高僧たちもみな携帯電話を持っていた。街行く車は、かつてのソ連製のオンボロ車はほとんど姿を消して、みな格好良い日本製(ただし、中古車)に変わった。まさに「隔世の感」である。 ▼モンゴル仏教との交流史 70年間にわたる社会主義政権下のモンゴル国内で唯一存続を許されたガンダン寺院と三宅家との関係は古く、米ソ冷戦対立下での世界平和をめざしてクレムリンでソ連のブルガーニン首相と核軍縮について直談判した私の祖父(三宅歳雄)が、モスクワからの帰途、モンゴルを訪問した1957年に遡る。当時、一修行僧であった現ハンボ・ラマのチョイジャムツ猊下は、その時のことを思い出し、以後、社会主義の厳しい時代も絶えることなく7・8回にわたって行われた三宅家との交流の歴史について触れ、三宅歳雄の孫である私の来訪を心から歓迎してくださった。 チョイジャムツ猊下との会談に続いて、今宮戎神社の津江明宏師と私は、同寺院において、世界平和を祈願して日蒙合同の礼拝を行った。これも、モンゴルを訪問した際には恒例になっているが、四六時中読経の絶えない本堂の中で僧侶たちと一緒に平和を祈った。この様子をこの日、ガンダン寺院に詣でた数多くの参拝者が見守った。 モンゴル国内では、同寺院を除くすべての仏教寺院が社会主義時代には破壊されたが、そのような逆境の中で、ガンダン寺院は懸命にモンゴル仏教(チベット仏教と同系統)の伝統を守ってきた。1992年の社会主義崩壊以後、7年間で全国に140カ寺が復興し、仏教が急速にモンゴル国民の心を捉えている証拠に、社会主義時代にソ連によって持ち去られた大仏(観音菩薩)が返却されなかったので、全国民的寄進を集めて、2年前には新たに高さ26メートルの巨大な観音菩薩像が大仏殿内に再建された。また、同寺院に保管されている百万部に及ぶ貴重な経典類(チベット大蔵経等)が新たにコンピュータを導入してインデックス(索引)が作成されているところを見学した。 ▼文化財の保存のお手伝い 続いて、われわれは同国第二の寺院であるタシチョリン寺院を訪問し、ダムバジャフ管長と会見した。同国大統領の諮問機関である宗教審議会の委員でもあり、WFB(世界仏教徒連盟)の副会長でもあるダムバジャフ管長は、1992年の社会主義政権崩壊以後、信教の自由と引き替えに、本国ではカルト集団だと見なされているような諸宗教が海外から一挙に流入し、モンゴル国内で伝道活動を行っていることの弊害(一般国民には、これらのカルトに対する免疫がないので被害が出やすい)や、資本主義体制の下での法体系の再構築を進めている同国の宗教法人法制定に伴う公益法人としての税制の問題等について、これらの問題に詳しい私と意見交換を行った。 さらに、われわれは国立ウランバートル大学仏教学科内に暫定事務所を構えるモンゴル仏教学研究所を訪問。大阪国際宗教同志会と三宅サイドがモンゴル仏教学研究所との協力事業として1998年から2000年にかけて三年計画で実施されている「モンゴル仏典保存復刻事業」の視察と、今後の研究事業のあり方について、同研究所のルブサンツェレン所長はじめ3名の仏教学者と意見交換を行ない、協力金の贈呈式が行われ、深く感謝された。市場経済化によって、信教の自由は保障されたものの、貴重な文化財の国外流出が進み、今ここで何らかの措置をしないと、中世以来、保存されてきたチベット仏教の経典類が散逸してしまう恐れがあるので、協力させてもらうことにした。 翌9日には、ウランバートルから80キロ離れた雄大な自然に囲まれたティレルジを視察。遊牧民の生活や民衆宗教に触れた。また、ウランバートル郊外の日本人墓地にも参拝した。この墓地には、先の大戦後、ソ連軍によってモンゴル国内に抑留されて死亡した数百名の元日本兵が眠っており、きれいに整備されている。われわれと入れ違いの形でモンゴルを訪問した小渕首相も参拝した。11日から始まるモンゴル民族の祭典「ナーダム(相撲・競馬・弓道等を競う国民体育大会のようなもの)」を見物するために数多くの日本人観光客がこの国に訪れているが、この中で、いったい何人の人が、わずか数十年前に、この地で戦争捕虜として過酷な条件(冬には氷点下20度以下になる)の下で強制労働をさせられ(現在でも立派な官庁街の建物はたいてい日本人抑留者が建設した)多数が死亡したことを知っているのであろうか。世界平和と諸国の均整の取れた経済発展をあらためて祈念せずにはおられない。 ▼遊牧民と農耕民の結婚? この文章の最初の部分で、「その晩(1986年)に見た星空(「宇宙にはこんなにたくさんの星があるのか?」と思えるくらいの「満天の星」があり、とりわけ星々の密度が高い「天の川」の部分が本当に「Milky Way(銀河)」と呼べるほど白くハッキリと「川状」に見えた)が、その後、私をモンゴルに引きつけるひとつの要因になった」と書いたが、その意味では、今回の訪蒙を私はすごく期待していた。なにせ、到着日が、7月7日七夕の夜だからである。近年、日本の大都市では、一等星以外の星はほとんど見えなくなった。その上、この時期は梅雨の最中で、天気が悪い。ここ数年は、子供たちと一緒に、庭から竹を切ってきては、短冊を書いて、七夕飾りを作っているが、本来ならうっすらと見えるはずの「天の川」はもとより、明るいはずの一等星である織女(ベガ=織り姫)も牽牛(アルタイル=彦星)すら見えないことが多い。 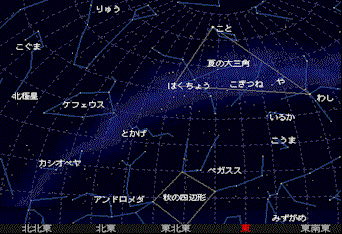 神話の時代以来「豊芦原の瑞穂の国」に暮らすわれわれ日本人にとって、最も解りにくい文化のひとつが、遊牧民の文化である。豊穣な恵みをもたらす大地というものを大切にするわれわれの文化(価値観)と、土地は誰のものでもなく遥か天上におわす神と個々の人間が契約を交わすという遊牧民の文化から出たユダヤ・キリスト・イスラム教などの文化(価値観)は、根本的に異なる。そういう意味からすると、年に1度の牽牛と織姫の出会いは、遊牧民族と農耕(養蚕)民族の結婚、ひいては、一神教と多神教のとも出会いとも考えられるます。広大なモンゴルの夜空のもとで、人類の2大文明が、衝突ではなく天では仲良くしている姿を目に焼き付けておこうと思った。 そんな訳で、子供たちには悪いが、天の川を挟んで、1年に1度だけ公然と「逢い引き」をする織女と牽牛を見に、七夕の夜にウランバートルを訪れたが、結果は、なんと曇天! 今回、合計60時間程モンゴルに滞在したが、ほとんど曇りか雨(現地の人も「今年はよく降る」と言っていた)ばかりで、昼間に2時間ほど晴れただけで、肝心の天の川はおろか、滞在中は、ひとつの星すら拝むことができなかった。因みに、放送衛星という「人工の星」を通して、ホテルで見た日本のNHKニュースは、全国各地でスッカリと晴れた「七夕」の話題を放送していた。 |