◆自然と生命と人間
 講師の中村桂子博士
講師の中村桂子博士 |
科学という分野と宗教というものとは、ただ今、司会の方からも、「どこに(考え方の)基盤を置くか(の違い)である」という話が出ましたけれども、世間では、一般に「全然、違うもの」のように言われています。
しかも、本日は、いろいろな宗教的背景を持たれた方がいらっしゃるし、それを私がどう受け止めていいのか、なかなか分からない……。ただもう私は、宗教のことは、正直申し上げて、何も解りませんし、とりたてて何も勉強していません。それから、(宗教的態度についても)典型的日本人です。「あなたはどういう信仰を持っていますか?」と聞かれると、何か特定のこと(宗派・教団)をきちっとお答えできる状態ではありません。もちろん、父母(の遺骨)は、鎌倉にございます円覚寺というところに眠っておりますので、時々、そこにお参りして、和尚様からお話を伺ったり、そういうこと(墓参)はいたしておりますけれども……。そして、そういう行為は私にとってはたいへん大事な行為でありますので、いわゆる「何も信じるものがない」という状況ではありませんけれども、だからといって、きちっとした教理を学んで、「こういうものが私の宗教的信念でございます」というものはないという意味で、典型的な日本人の状況であります。

中村桂子博士の講演に耳を傾ける
国宗会員諸師 |
そういう人間が語ることですから、正しいとか正しくないとかは別にして、「宗教と科学」というのは、あんまり違わないものじゃないかと私は思っています。といいますのは、ただ今ご紹介いただきましたように、私は生命誌というものを研究いたしておりまして――それは何を研究する学問なのかということについては、後で聞いていただくつもりですけれども――そもそも、私が科学者として知りたかったことは何かって言えば、やっぱり「私ってなんだろう? 私はどういう存在なんだろう?」ということと、自然というものを見ていると、本当に大きなものだけれど、「これはいったいどういうものだろう?」という疑問、それから、生命というものの不思議さについてですね。
ですから、私の研究のテーマは「自然と生命と人間というものを知りたい」ということなんです。とにかくよく分からないことが多いんですけれども、「とても知りたい」というのが私のテーマです。そして、なんとかしてそれに少しでも近づくために――いろいろな近づき方があるのですけれども――私は自分の性質上、科学という方法でアプローチをしているのです。ただ、後でお話ししますけれども――科学というものに、皆さん一定のイメージをお持ちかと思いますが――一口に科学と言ってもだんだん変わってきているし、また、変わらなければならないというふうに私は思っていますので、その辺までお話ができたらいいなあと思っています。
◆20世紀をふり返ってみて
実は、こういうこと(自然・生命・人間)が知りたい。こういうものが私にとってとても大事だ。というふうに思っている人間から見ますと、私自身が生きた二十世紀という世紀は、こういうものをあまり大事にしなかった世紀だというのが、私の実感でございます。
では、「20世紀は何の世紀だったか?」ということを皆さんがひとまとめにおっしゃるときに、一番よくおっしゃるのが、ひとつは「戦争の世紀だった」という括(くく)り方です。戦争でこんなにたくさんの方がなくなった世紀はないだろうというのがひとつですね。これは、明らかにこういうもの(自然・生命・人間)を大事にしているとは思えない行為です。
しかし、人間の本質の中にそういうものがあるから、こういうこと(戦争)が起きるのだと思うと、そこをただ、「だめではないか」と言っていられない。「何故そういうことをする本性が私の中にあるのだろう」ということを考えなきゃいけませんけれども、やっぱり、こういうものを大事にしているとは、どうしても思えない。
それから、よく言われますのが――これが私に直接関わりがあるわけですけれども――戦争といいましても、昔のように相手と直接、対峙して「やあやあ、われこそは……」というような合戦ではなくて、最近の戦争は、ボタンを押すような戦争になってしまいました。ですから、「20世紀を象徴することを言いなさい」と尋ねられれば、もうひとつの言い方をすれば、「科学技術がとても進歩した時代だ」と、こんなふうに言えると思うんですね。戦争も科学技術による戦争……。
しかも、20世紀という時代は、どうもこういうもの(自然・生命・人間)を大事にしなかった。となると、その20世紀の科学技術というものも、こういうものを大切にしようとする観点からすると、悪いものではなかったのかということになってしまうのです。それは、科学や技術のあり方というのが、本当はひとつしかないのではなくて――20世紀の科学技術は確かにそうだったけれども――私は、そうではない技術のあり方というのを求めてきたのです。
では、なぜ今のような研究分野の仕事に入ったかというと、まずひとつは、人間という存在がやっぱり私の関心の中心にあるわけです。科学技術的な言い方をすると、自然というものは、人間が登場する以前からあるわけですね。「人間が登場する」と申しますのは、自然界(地球)というものが――地球は45億年前にできた星だと言われていますが――そこに生き物たちが生まれたわけです。この地球という星に、私たち人類と呼ばれるものが登場したのは、原人と呼ばれるものでも500万年前、現代の私たちと同じようなホモ・サピエンスはというと、わずか20万年前です。したがって、私たち人間がこの地球上に登場したときには、今、存在している他の生きものたち、ほとんど全部(の種)がこの地球上にいたわけです。私たち人間はいちばん後から出てきたものなわけです。
◆人間が名前を付けた生きものはわずか3%
ですから、自然というものは、人類がこの世に登場したときには、既に存在していた。その中で私たち人類は生きてきたわけです。その生き物の中で――実にたくさんの生きものがいます。その生きものの数が今、まだ正確には判っていないんですが、「5,000万種くらいいるだろう」と、いうふうに言われています――そのうち、私たちが名前を知っているのは150万種だけです。
長い間、主としてこういう作業(命名・分類)をしてきたのは、ヨーロッパの人たちでしたが、これらの作業は、ギリシャ時代ぐらいから始まりました。2,300年程前にアリストテレスという人がいましたけれども――私は、彼は哲学者だと思って、永らく遠くに置いときましたが、いろいろ調べていくうちに、どうしても(彼について知ることが)必要になってきました――アリストテレスという人は、「生物学者の祖」だと思います。彼は『動物誌』という書物を書きましたが、たとえば『動物誌』の中には、鯨はちゃんと哺乳類に分類されていて――私だったら「泳いでいるから魚かな」と思うでしょうけれども――アリストテレスは、徹底的に調べて、ちゃんと「赤ちゃんを産む」ということを見て、哺乳類の中に入れてるとかですね。そのころから、生物のことっていうのは、本当によく調べられていて、そこから、いろいろな生きものに全てに名前を付けてきた訳ですけれども……。人間が3,000年くらいかけて付けてきた生きものの名前の種類は150万種類です。
けれども、実は、こういう名前をつけてきたのは、ヨーロッパ、アメリカ、日本なども含めて、いわゆる先進国の人たちでしたから、たいてい温帯地方にいる。したがって、その辺のところはよく調べられているのですが……。最近、熱帯が注目されるようになって、熱帯を調べるようになってきました。そうしましたら、状況はまるっきり変わってきました。熱帯の中でちょっと調べてみますと、たとえば、ある一本の木に棲息している虫などを調べてみましても、そこにいる虫を全部採りまして、世界中の専門家が眺めてみたら、名前が付けられるものはたった3パーセントしかなかったそうです。ということは、逆にいえば、97パーセントは、世界中の昆虫学者が集まっても見たこともないもの(新種)だったのです。
だから、私たちは「学問が進んだ、進んだ」といいますけれども、これは、私たちはいかに、まだ何も知らないか……。ということのひとつの証拠だと思うんですが……。97パーセントが未解明ということが判ったので、そこから類推していくと、どうも地球上には5,000万種類もの生物がいるんじゃないかということになっております。
そのうちのひとつが人間なんですけれども、私たち生物学者は、そういうものを自然の中にいる状態でのホモ・サピエンスと呼び、日本語では「ヒト」と書きます。そして、こういう建物を建てたり、洋服を着たり、宗教を持ったり、学問をしたりする状況になったものを「人間」と呼んでいます。ですから、生(なま)の生きものとしての存在を「ヒト」と呼びます。その「ヒト」としての人間は、本当は自然の一部なんです。
◆ヒトとしての人間
「ヒト」という生きものは、ただ今、申し上げたように、5,000万種類の中の一種なわけです。自然の中というのは厳しい。他の生きものたちとの競争というのも、そんなに甘くない。ですから、生物というのはひとつひとつが自分の能力を思いっきり活かして生きていかなければならないのです。チータは「早く走れるぞ」という能力を使わなければならないし、イルカは「泳ぐのが上手だよ」という能力を使わなきゃ生きていけないし、ワシは飛ぶ能力が必要だし……。といいますと、ヒトという生きものは、生物学者から見ますと、飛べないし、走るのも早くないし、泳ぐのも得意でない情けない生きものです。
けれども、ヒトというものに与えられた――宗教的に言うと、神様が与えて下さったという力――科学者から言うと、自然が与えてくれた能力というのは何かということを考えると、やはり、そのズバ抜けた頭脳と言えるでしょう。ヒトは直立二足歩行したために脳が非常に大きくなりました。両手が自由になりましたし、大事なことは、言葉が話せるようになりました。この言葉が話せること、脳でいろいろ考えられること、手でものがいろいろ作れること。これらの能力が「あなたたちはこれを上手に使って生きていきなさい」というふうに、自然から私たちヒトに与えられていると、生物学者としては思わざるを得ないのです。
そうしますと、その能力を使えば、石器を使うというところからはじまって、技術を開発して、そして農業をし、工業をやり……、と発達してきたのであって、人間が技術を使うということ自体は、悪いことではないわけです。「20世紀は科学技術の時代であった」と、私は先ほど申し上げましたけれども、それを否定してしまうと、生物学者としては、人間は「ヒト」であることを否定しなければならないので、それはできません。
ただ、なぜ私が20世紀の科学に対して疑問を持つかというと、その科学技術が――科学技術というのは、ある種の「人工の世界」を創ることです――この人工の世界と自然との関係に疑問を持つからであります。自然というのは、恐いもの。地震もあれば、いろんな災害があります。それから、日常的に言えば、今日も外は寒いですが、「寒いの嫌だ。暑いのは嫌だ」となると、面倒くさいですから、間に「人工」を入れれば、ぬくぬくと暮らせる。そして、「自然からできるだけものを取り上げて、間に人工を入れれば、人間はぬくぬく暮らせるじゃない」というところに科学技術を使ってきました。
けれども、人間という存在は、実は、自分の中に「ヒト」という動物の部分を持っているのですから、しかも、この「ヒト」は完璧に自然の一部なんですから、「自然の中に自分はいるんだ。間に人工を入れてはいけない」という考え方も合理的なもののひとつです。けれども、いろんな技術を使って新しいことをやったり、暮らし易くしたりはする。そういう力も与えられているのだから、そういうものを使って世界をある程度作って暮らし易くしていくことは、人間というものはこの人工の世界に繋がっているのだから、いいのだけれども……。
一方で、この「ヒト」という部分が自然の中にあるのですから、人工を間にいれてぬくぬくとして、自然を敵対するのではなくて、「これを考えながら、それにうまく合うような人工を作っていこうよ」ということをやる。本当は、それが人間としてやることだったのではないか、と私は思っています。そして、この人工と私が書きましたのは、今、「科学技術」と言ってきましたから、皆さん建物とかのことを考えますけれども、それだけではございません。政治のような制度、学問、宗教みんなある意味では、自然のままのものではなくて、人間が創っていくものですから人工ですけれども。この人工を自然に対立するものではなくて、「自分はヒトというものなのだから、十分その事実を踏まえた上で、そういうものを創っていこうよ」と、そういうやり方をすればいいのではないかと私も思っていることです。
◆すべての生きものに共通するものは何か
そこで、「ではどうすればいいか?」というと、実は、私たち人間は、「ヒト」という生きものについてこのことをよく知らないと、どうしていいか判らない。「ヒトというのは自然の中でどういう存在なんだろう?」ということを知らない限りそれはできないわけですから、まずスタートするのは、「ヒトというのは自然の中でどういう存在なのか?」ということを知るところから始めようと思いました。

扇形図:「生命誌」的世界観の概念図 |
それが、本日お配りいたしました冊子の表(図1)にあります。この扇形の図を見てください。これはある意味、答えではありません。「人とは何か?」なんて全然判っていません。けれども、こういう形で考えていこうというふうに思います。それは、どういうことかと言いますと、ここ(図の左上端)にヒトが描いてあります。そして、この右端にバクテリアが描いてあります。別に、なんでもいいです。キノコでも、イモリでも、イルカでも、ゴリラもいますし、どこをご覧くださってもいいのですが、ここ(扇形の弧の部分)に5,000万種類くらいの生きものがいる。ここ(弧の部分)が現在です。
ちょうど、私がこの分野(生物学)に入った頃に見つかったことなんですけれども、先ほど申しましたように、5,000万種類もの生物がいる。それは多種多様な植物だったり、動物だったり、バクテリアだったり、動物の中でも、カエルだったり、イモリだったり……。ほんとに様々な姿をしているけれども、生きているってことでは共通なわけです。片一方でめちゃくちゃ多様性があるのに、片一方で生きているという点で共通であるという、一見、相反する特徴があるので、何かそれを結ぶものがないといけない。
そこで、科学はその共通の部分を探しました。そして、その共通の部分が今ではハッキリと見つかりました。まず、生きものの共通の部分は「細胞」という部分です。ちょっと科学的な話になってしまいますが――脳細胞や心臓の細胞とかいった用語を、皆さんも日常的にお使いになるかと思いますけれども――すべての生きもので、細胞というものでできていない生きものはひとつとしてありません。
たとえば、バクテリアは、たった1個の細胞からできている。ですから、単細胞生物といいます。時に、人間の中にも、単細胞的な人がいなくはない(会場笑い)ですが、実際には、人間は多細胞生物です。誰もすべての細胞の数を正確に数えたわけではありませんが、細胞1個の大きさが判っていますから、その細胞の大きさから計算しますと、1兆個の細胞を集めるとだいたい1キログラムになります。そんなものだと思って下さい――そうはいっても、100グラムのビフテキを召し上がるときに「これは細胞何千億個分かな?」と思うとおいしくないので(会場笑い)、そんなことはなさらなくてもいいですけれど――1キログラム1兆個としますと、成人1人の体重が60キロだとして、ヒト1人を構成している細胞の数は、60兆個というふうになりますね。
生物で細胞でできてないものはない。しかも、そのすべての細胞の中にDNAというものが入っていて、このDNAというものが、その細胞の性質を決めるんだということが最近、ハッキリしてきました。ですから、DNAを持っていない生きものもいません。生きものがDNAを持っているという事実は、その生きものがこの扇形の図表のどこにどういようとも共通です。ですから、DNAを持っているという点でこんなに共通でありながら、どうやってこんなに多様な種になっているんだろうということが問題になりました。
◆ すべての生きものはゲノムを持っている
すべての生きものが持っているひとつひとつの細胞の中に入っているパッケージとしてのDNA全体のことを――ここでは細かいことは説明しませんが――「ゲノム」と呼びます。これは、脳の細胞にも心臓の細胞にも、身体を構成する60兆個の細胞全部に同じゲノムが入っているのです。
では、「同じゲノムはどこから来たか?」というと、もちろん「いのちのはじまり」とは、生物学的に言えば、受精の瞬間です。受精卵というものは一個の細胞です。これは、非常におもしろいことです。普通、1個1個の細胞というのは、キチッと独立しています。心臓の細胞は心臓の細胞で独立しているんです。もし、細胞同士がぐじゃぐじゃ一緒になったのでは、たいへんなことになります。ところが、たった1種類だけ、別の細胞が一緒になる細胞があります。それが、精子と卵です。この2つの細胞だけは、なぜか一体化する。そんな細胞は他にはありません。一体化した結果、1個の細胞になるんですね。ですから、受精卵というのは1個の細胞。その中には、もちろん、ゲノムが入っている。そこに入っているゲノムが、皆さんの性質を決定づけ、動かしてゆく設計図なのです。
では、「このゲノムはどこから来たのか?」と申しますと、今、申しましたように、精子と卵から来たわけですから、精子の中に入っていたDNAと、卵子の中に入っていたDNAとが一体化して、受精卵のDNAになったということです。そして、その精子と卵は、両親にそれぞれ由来するものです。その両親の精子と卵はどうやってできたか? というと、これは、精子は父親の細胞、卵は母親の細胞ですから、それぞれがまた、その父親と母親からもらっていることになるわけです。そうしますと、それぞれの皆さんが今、持っておられるゲノムはどこから来たか? っていうことになると、ずっと遡(さかのぼ)っていったら、たぶん日本人の祖先はどこからきたか? ということになります。
そこからさらに進んで、人類の先祖はどこから来たのか? ということになると、現在の科学では、「ヒトはアフリカから出た」というふうに、DNAの研究によって判明しています。ですから、今、生物学では、人種という言葉は申しません。民族はありますが、人種はございません。ヒトというのは一種だけです。たとえば、蝶々という生きものは2万種も知られています、モンシロチョウがいたり、アオスジアゲハがいたりと、それぞれの種が違います。チョウは2万種類くらいいますが、「ヒト」という種は一種類だけです。ヒトという生きものの見た目はかなり異なりますが、それは、長い間、ある特定の環境に暮らしていれば、そこに適応して、暑いところにいる人は肌が黒いほうが有利ですし、寒いところにいる人は鼻を高くして、いったん鼻腔に吸い込んだ空気を温めた後に肺に吸入したほうがいいので鼻が高くなっているというふうに、いろんな解説があって、それぞれ少しずつ見た目の様子が違いますが、DNAで見る限り、それぞれの民族の間に全く差はありません。
◆ バイオヒストリーという考え方
話を元に戻しますと、人類の一番最初はどうしてできたのか? というと、科学では「チンパンジーの仲間から来た」ということになっています。これをどんどん、どんどんと遡って、「ここが生命の起源です」という時点まで行くと、これは、だいたい38億年前まで遡ることができます。キノコだって、ある日突然、ポコッと生まれたわけではなくて、最初の生きものから始まって、だいたい、この辺(註=扇形の図表の中頃を指して)ぐらいまでは、ヒトと同じ道を歩いてきたのですが、ヒトはだんだん動物のほうへ向かい、その中でも、背骨のある動物に向かい、だんだんカエルみたいになり、というふうにして私たちヒトはできてきたのですが、一方、キノコは、この辺から、いわゆる菌類のほうへきた。扇の要の位置からの距離が時間軸で、横の距離の違いがDNAの隔たり具合です。
ですから、現在、生きている生きものたちのDNAを分析しまして、どのくらい似ているかを調べればいいんです。先ほど私は「ヒトはチンパンジーの仲間から来た」と申しましたけれども、チンパンジーとヒトのゲノムの差を比較したら、ほとんど同じ。もちろん、キノコとはだいぶん違います。しかし、だいぶん違いますけれども、同じところもある。ということは、この図に描いてある生きものたちはすべて、ここ(扇の要の位置)から出て、38億年かけて今の状況(扇の弧の位置)にあるということです。
ですから、生物学的に「私というものを知りたい」という時には――これですべてが判るわけではございませんが――少なくとも私たちがここまでどういうふうに来たのかという尺度、それから、他の生きものたちと私はどういう関係にあるのか? ということは、このゲノムを分析して調べていくと、本当にたくさんのことが判ってきます。これを私は「生命誌(バイオヒストリー)」と名付けて、それを読み説くということが――まだ全部は読み説けていませんが――私という存在が、自然の中でどういう位置にあるのか? ということを知ることにつながります。
また、これからの自然をどう考えていったら良いのだろうか? というときに、今ここにある自然だけを見て、「あそこの緑は大切に」とか言うことも大事ですけれども、むしろ40億年近い流れの中で、この地球はどうなっているんだろう? その中で、みんな(他の生きもの)と一緒に暮らしてゆき、次を壊さずに、次の時代へいくのにはどうしたらいいのだろうということを、ここから読み取ろうということが、私がやりたい、また、今、行いつつあることです。これが、本日、頂戴した『ゲノムからみた人間』というテーマの「ヒト」ということをきちっと意識した上で、私たちは人間として暮らしていくのがいいのだろうなということが、ゲノムということを調べるところから出てまいります。
そこで、簡単に申し上げる時のゲノムの意味ですけれども、いくつか、そこから派生することを少しお話しします。本日のテーマに書いてあることで申しますと、皆様も、「遺伝子」という言葉をほうぼうでお聞きになると思います。私は先ほど、「すべての生きものに細胞がある」と申しました。そして、「そのすべての細胞の中にDNAが入っている。その全体をゲノムという。これは親からもらうのだ」と申しました。生きものじゃないもの――マイクでもいいです、机でもいいです――と、私たち、生きているものを比べてみますと、生物的に申しますと、生きものの特徴というのは、とにかく「続いていく」ということです。生きもののいろいろの状況を調べていくと、アリ1匹見ていても、よくできてるな。キクの花を見ていても、なかなか巧くできているな……。と、どれを見ても感心することがございますけれども、結局、突き詰めていくと、巧くできているのは何のためにできているかといいますと、やっぱり「続いていくことができるように」という意味で、とても巧くできている。それで、40億年とにかく続いてきたわけです。
◆「続いていく」ということが生命の意味
生きものの歴史を見てみますと、次々と新しい生きものたちが生まれて、多様化してきた歴史がありますけれども、同時に、途中には、たくさん絶滅ということもありました。生きものの歴史を調べていけば、ある意味では「絶滅の歴史」と言うことができるくらいです。その中でも、わりあいと有名なのは、今から6000万年前に(註:大きな隕石の衝突によるとされる)、恐竜をはじめほとんどの大きな生きものたちが滅んだことですが、この時にかろうじて生き残ることができた小さな生きものたちの中からヒトの祖先が生まれてきた。
その他にも、この6000万年前のできごとだけでなくて、たとえば2億年くらい前には、「スノーボール」といって、地球全部が氷の塊になった時期があった(註=多くの生きものが絶滅した)ということが、最近では判ってきました。この40億年間には、そんな厳しい歴史が繰り返されてきたわけですから、決して生きものたちはのほほんとして生きてきたわけではなくて、「その時点で地球上にいた生きものの90パーセント以上は消えてしまった」というような、過酷な自然状況に遭遇することが何度もあったわけです。
けれども、そういう厳しい環境の中でも、「生きものが全部絶えてしまった」ことはありませんでした。それはなぜ判るかというと、すべての生きものが共通して持っているDNAを見れば、私たちがそういう歴史を持っているということが判りますから、それを追っていくと、決して、全部の生きものがなくなったというわけではない。40億年近くも、なんとかして綿々と続いてきた。この力は凄いものだと思います。生きものが持っている生命の力っていうのはともかく凄い。続いていくということのために、どんな小さな生きものたちも凄い力を持っていると思います。
そうしたら、続いていくというときに、具体的にどうやって続いていくかと申しますと、もちろん、時々、新しい生きもの(新種)も生まれているんですけれども、原則は、親と同じものをコピーしているわけです。牝犬が懐妊すれば、私たちは当然、「イヌの子が産まれる」と思っています。「イヌからネコが産まれる」とは誰も思っていない。ですから、原則的には、同じものを続けていく。しかし、その中で少しずつ、少しずつ変化していく……。
まだ生物学がなかった時代でも、昔の人でも、それくらいのこと、すなわち、「親の性質が子どもに伝わる」っていうことは、分かっていた。それを科学的には「遺伝」と呼んでますね。「親の性質が子どもに伝わるのは、どうやって伝わるんだろう?」ということは、昔の人にとっても、とても不思議だったわけで、「体液が流れていて、その体液にある性質があって、それが子どもに伝わるんだろう」とか、いろいろ理屈が考えられていたんですが、19世紀の終わり頃にメンデルという人が出て、「遺伝子というものがあるんだ」ということが判ってきました。もっとも、彼は、これを遺伝子とは言いませんでした。彼は因子(エレメント)と呼びました。「体液のようなものを出すんじゃなくて、ある特定の性質を持ったエレメントがあって、それを次々と渡してゆくんだ」と彼は言いました。それを今日、われわれは「遺伝子」と呼んでいるわけです。
◆決められたものではなく創り出すもの
私はこの遺伝子という言葉が気に入りません。実は、メンデルはオーストリアの人ですが、その頃はドイツで学問が盛んでしたので、たいていの学術用語はドイツ語になりました。もともとのドイツ語では「ゲン(Gen)」と名付けられましたが、今は英語が国際語ですから、英語ではこれを「ジーン(Gene)」と申します。その伝えるもののことですね。先ほどから、私は「ゲノム」と申しておりますが、実はこれはドイツ語でして、この頃では、英語ふうの発音で「ジーノム」とも呼ばれています。これは、「遺伝子の集まったもの」という意味です。日本語で「遺伝子」と言っても全然ピーンと来ませんけれど、元を言えばジーン(Gene)であり、それが集まったものがジーノム(Genom)です。
ところで、この私たちが遺伝子と呼んでいるものは、何をしているかというと、DNAは、両親からもらったものです。ですから、私たちは、遺伝子を両親から受け取りますけれども、これが、ただ「受け取っただけか」というと、受精卵が分裂して、そして脳を作り、腸を作り、皮膚を作って――細胞は何もかも、みんな両親からもらった遺伝子をもとにして動いて――いるわけですけれども、だからといって、それ(遺伝的要因)だけだとは、言えないわけです。
それは、例えば、背の高さがどうなるのかということが予めみな決まっているのかというと、日本人を見ても、いろんな年齢層によって、脚の長さなんかもずいぶん変わってきていますよね。若い人なんか同じ身長でも全然、脚の長さが違っていて、いつも羨(うらや)ましそうに眺めるわけですけれども…。そういうのは、やっぱり成長期の栄養とか、生活の仕方によって変化するものなのです。みんな親から同じもの(遺伝子)をもらっているはずなんですけれども、そんなに急に日本人の遺伝子が変わったはずはないんですけども、生活の様式とか栄養の良し悪しとかいうもので、たしかに姿形も違ってきてますよね。それから、脳の中でもDNAが働いてるんですよね。そういうものがどういうふうにして脳を働かせるのか? 私のように宗教をあんまり勉強していない人もいれば、皆さんのようにきちっと考えておられる人もいるというふうに…。ですから、遺伝子は一生の間、それが体の中で動いてゆくのですね。
そういうわけで、日本語の「遺伝子」という言葉には、どうも「予め決められている」というようなイメージが付いて来ます。ところが、このジーン(Gene=遺伝子)というのは、もう、宗教家の皆さまはお気付きだと思いますけれども、『ジェネシス(Genesis)』というと、これは旧約聖書の冒頭にある「天地創造」の神話が収められた『創世記』のことですよね。ですから、ジーンというのは「創り出す」という意味です。
ということは、英語でジーン(Gene)ということをお聞きになれば――もちろん「親からもらうもの」ということが、学問的に判って、そういうものに名前が付いたのですが――英語を話す人にとっては、言葉から見ると、「予め決められる」というよりは「創り出す」というほうが、たぶんイメージ的に強いと思います。中国のほうではこれを「起因子」と呼んでいます。これはなかなか良い翻訳だと思います。ともかく、私たちを創り出していくものだ。ですから、私自身はどうも、日本語の遺伝子は名前が良くないと思っていて、どなたがお付けになったかは知りませんが、「そうじゃない名前が付いていたら良かったのにな」と思います。そして、遺伝子もそういうものの集まりだというふうに思います。
◆生命はゲノム単位で考えるべき
私たちが持っているゲノムというのは「遺伝子の集まり」のことなんですけれども、遺伝子というものを基本にして考えると、私たちの存在は、そういう遺伝子という因子の集まりということになります。しかし、私はそうではないと思います。生きものというのはまるまるでなければなんの意味もない。それを分かりやすく申しますと、例えば、犬が歩いているとします。その犬は細胞からできています。その中に犬のゲノムが入っています。猫がいれば、その猫はゲノムを持っています。ですから、私が自然界を見れば、犬がいたり、猫がいたり、菊が咲いていたりするのですけれども、それは、犬のゲノムがあったり、猫のゲノムがあったり、菊のゲノムがあったりというふうに見えてしまう。しかし、遺伝子というものは、自然界に、遺伝子だけ単独で存在することはありません。
遺伝子というのは必ずゲノムというものを構成する。遺伝子が集まって、ヒトの場合はだいだい3万から4万くらいの遺伝子の集まりです。そういう遺伝子の集まり、その全部をゲノムというのですけれども、この1個1個の遺伝子が単独で自然界に存在することはありません。必ず、ゲノムの中にあります。もちろん、私たちは研究室の中で、DNAを取り出してきて、この遺伝子だけを調べようと思えば、それを試験管の中で調べることはできますけれども、自然界にはそういう形では存在しません。ですから、DNAを考える時は、ゲノムが単位です。生きものを考えるときには細胞が単位です。
細胞は生きています。細胞を生かす働きをしているのが、ゲノム全体です。遺伝子というのは、別に1個あったからといって、これだけで何か生かすということはできません。生命ということ、生きているということを考えるなら、細胞を考えなければなりませんけれど、もし、DNAで考えるのなら、ゲノム単位で考えなければいけません。まだオーソライズはされていませんが、私は、これを勝手に「生命誌」と呼んでいます。もし、何か単位として考えるのなら、ゲノムを考えるべきで、それより小さな粒で生きものを考えてはいけない。
ところが、この頃やたらに、遺伝子とかDNAという表現がはやってますね。もうなんでも、自動車もDNAです(註:ホンダのコマーシャル)し、昨日は私の事務所に「京都のDNA(会場笑い)という番組を作るのですが……」というファックスがKBS京都放送から来ました。とにかく、DNAとか遺伝子という言葉が氾濫(はんらん)していますが、この氾濫のほとんどは、(DNAとか遺伝子の意味は)「予め決まっている」という感覚で使われていますよね。
しかし、本当はそうではありません。本当にこれだけ長い間続き、他の生きものたちと関わり合いを持ち、こういう世界を創っていくためのさまざまな作業を新しくやっていく仕組み……。そして、時には自分自身が変化して、新しい生きものを生み出していくのがゲノムであり、それが生きるということを支えているわけです。しかも、それはあらゆる生きものに共通しており、その中に「ヒト」という生きものがあり、そして「人間」というものが存在しているわけですから、そういう形でDNAというのを見ていくということが、私の人間存在に対する考え方です。
もちろん、それだけが人間を見る目ではありませんけれども、この限られた時間の中で、一番基本的なところを申し上げれば、そういうことになるかと思います。お話をしようと思えば、いくらでも申し上げたいことがございますが、先ほど、申し上げましたように、こういうお話は、皆さん日頃はお聞きにならないだろうし、日常の中でゲノムについて疑問に思ってらっしゃることというのがたくさんございますでしょうから、一応ここでお話を止めさせていただいて、ご質問とかご意見を伺って、また、それに対してお話をさせていただきます。
(講演終わり 文責編集部)
大阪国際宗教同志会 平成十五年度総会 質疑応答
『ゲノム(遺伝子情報)から見た人間の意味』
JT生命誌研究館 館長
中村桂子
三宅善信: 中村先生、ありがとうございました。38億年にわたる話を50分間でしていただき、生命誌という考え方のエッセンスの部分を私共、素人にも解りやすくお話し下さいました。私もよく悪いことをして、「人でなし」と言われますけど、あれは間違いだったんですね。動物としてのヒトには、善いも悪いもない。本当は「人間でなし」(会場笑い)と言われるべきなんですね。
それから、中村先生のお話を承りまして、自然界には、かくも多くの未知の生命がいて、人間は自分たちは賢いつもりでも、まだ、生きもの全体の3パーセントしか判って(名前をつけて)いないということに驚きました。しかし、逆に言いますと、「名前を付ける」という行為が、ヒトではなく人間としての行為なんだなあとも思いました。
そうしますと、先ほど先生が、旧約聖書の『創世記(ジェネシス)』の話を出されましたけれども、『創世紀』の冒頭の部分に、有名な「アダムとイブ」のお話が出てまいります。最初に神が世界(天地、山川、動植物等)を創造してから、最後に人間(アダム)を創り、このアダムに世界にある生きものを見せて、それぞれに名前を付けさせるわけですよね。そして、アダムが「これは鳥と呼ぼう。これは花と呼ぼう」というように、「アダムが付けた名前がそのものの名前になった」と書いているわけですから、ある意味で、「正解」です。
もちろん、旧約聖書を書いた人たちは、遺伝子どころか、なんの科学的な知識もなしに全くの想像力だけで、この「よく出来た話」を作ったわけですけれども、あにはからんや「アダムがいきものに付けた名前を神がよしとされ」(『創世紀』第2章第19節)たということは、人間は名前を付ける存在だということです。名前を付けるということは、改めて自然の中にあるものを自由に切り分けて、それに意味を付与するという、きわめて人間的な行為なんだなと、思いました。
時間もございませんので、ただ今から質疑に移らせていただきます。ご質問のございます先生は、挙手をいただきまして、ご所属とお名前をお願いします。
葛葉睦山: 私は、高槻の山の中で、臨済宗のある末寺の和尚をしております葛葉睦山と申します。
中村桂子: 私共(生命誌研究館)も高槻ですから、是非一度、いらしてください。
葛葉睦山: 中村先生がお示しになられた『生命誌絵巻』という考え方は、独創的なものですね。私は、仏教に伝わる『仏涅槃図』のことを思い浮かべました。お釈迦様が入滅(亡くなる)される場面を描いた絵ですが、その中には、人間だけではなくて、いろんな動物から昆虫までいる、という風景が絵巻きになっている。それを思い起こしまして、われわれ仏教徒は、あらゆる生きものが平等であるということを教えてもらってきたといいますか……。
中村桂子: そう思います。私はお釈迦様のことは何も分かりませんが、お釈迦様はDNAも何もご存知ではなかったけれども、もう二千数百年も昔に、生命の本質を見抜いておられて、これ(『生命誌絵巻』に現された世界)とまったく同じことをお考えになっていた方だと思います。
葛葉睦山: そうですか。そうお聞きすればたいへん嬉しく思います。仏教では、「仏性(ぶっしょう)」ということを言います。「万劫(まんごう)にも受け難きは人身なり」という短い偈(げ)(註=仏教の真理を詩の形で表したもの)があるんです。万劫というのは、ものすごく長い時間の単位ですけれども、想像することもできないくらい長い生命誌の中で、幾千万の多種多様な生きものの中で、こうして人間として生を享けること事体、千載一遇の機会であるけれども、今こうして、私は人間として、ここにいる、ということをお釈迦様は『開経偈』で指摘されています。このことについて発展的なことをお聞きしたいと思います。
中村桂子: 例えば、お釈迦様は生・老・病・死という形で「生きる」ということをおっしゃっていますよね。生物学の研究をやっていますと、「生きる」ということと「死ぬ」ということの関係――もちろん、その中には、病も老も含まれていますが――を考えてみると、「生きる」ということの中に、既にもう老や死というものが組み込まれているのですね。即物的には、ゲノムの中にそのことが組み込まれている。生きるということは老いるということです。
具体的に申しますと、癌(がん)という病気がありますが、「癌という病気は何か?」というと、先ほど、私は「生命とは続いていくことだ」と申しましたが、続いていくためには、どうしなくちゃいけないかというと、細胞の立場からすれば、分裂をして殖えていくということです。例えば、「成長する」という時は、体の細胞が分裂して殖えていっているわけです。ですから、「細胞が殖える」ということは、「生きる」ということそのものなわけです。
ところが、「癌というのはどういう状態か?」というと、細胞がやたらに殖えていくのが癌ですね。そうすると、癌という細胞だけ見てみると、この細胞はものすごく元気なんです。こんなに元気な素晴らしい細胞はないんです。これを調べていくと、ゲノムの端っこにテロメアという部分がありまして、細胞が殖えていくためにはDNAも殖やさなくちゃいけない。そうすると、編み物のときと同じで、これをもう1本編んで殖やさないと次の細胞ができない。実際に編み物をやってみられたらお分かりになるかと思いますが、端っこがだんだん目を落としていって減ってしまうんですよ。DNAもこの端っこを殖やすのがへたで、端っこが減っちゃうんですよね。しかし、DNAの中で大事な情報があるところが減ってしまったら生命の存亡にかかわりますから、ここにテロメアという余分なものをくっつけまして、万が一これ(テロメア)を落っことして複製しても大丈夫(註=肝心の遺伝情報の伝達には影響がない)なようにしてあるんです。
テロメアという部分は、あってもなくても平気な安全装置のようなものなんですが、これが老化の原因のひとつになることが判ってきました。ところが、癌細胞には、テロメアーゼという酵素があって、テロメアの部分がなくなったらそれをまた殖やすことができるわけです。ですから、癌細胞というものは、細胞としては、もう素晴らしい細胞なわけです。なにしろ、老化しないようになってるんですから……。そこで、癌細胞を研究している人は、「これは凄い。この仕組みを全部解明したら、老化しないで済む」とか言うんですけれども、なかなかそういうふうにはいかないんですよね。
よくお考えになっていただくと、お解りかと思いますが、この細胞の能力は素晴らしいんですけれども、一部の細胞だけがめったやたらに殖えると、私たちの体全体としては死ぬわけです。例えば、肺の細胞は肺の細胞として、成長するときには、殖えなきゃならないし、皮膚の細胞なんかもどんどん新しいものと入れ換わって殖えていかないといけないけれども、大人になったら、もうそれ以上、殖えませんよね。DNAには初めから「ここで止めなさい。これ以上やっちゃいけません」という命令が入っているです。
ところが、癌の細胞というのは「これ以上やっちゃいけませんよ」という命令がなくなっている。ですから、癌細胞自体はすっごい元気な細胞なんですけれども、その全体の中で見るときに、「あなたはここなんだから、これ以上やると全体のバランスが崩れますよ」という情報を受け取る能力を失っているのですね。それで、この元気な細胞がめったやたらに殖えると、私たちは死んでしまうことになります。そうすると、もの凄く「部分がよく生きる」ということが、私たち「全体が死ぬ」ということになるのですね。ですから、「部分が死ぬ」ということと、「全体が生きる」ということは、まさに表裏一体の関係にあります。そんなようなことが、細胞というものを調べていけばいくほど、判ってまいりました。
そして、この中には、「老い」ということが入っておりました。その、生・老・病・死という4つのことから、どう人間というものを捉えるか? 宗教というものは、本質をパッと捉えられる。今は、たまたまお釈迦様のことで申し上げていますけれども、そういう宗教というものの中には――私たち科学者は、ひとつひとつ分析したりしていますが――本質を掴んでいらっしゃるなと、生物のことを調べれば調べるほど、そういう感じがいたします。
三宅善信:ありがとうございます。多くの宗教が説く、「足るを知る」ということが、生命の世界では、自然と、まさに細胞レベルで行われているということですね。驚きました。それでは、どなたか他にございませんでしょうか?
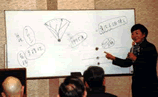
素人にも解りやすく図解して説明する中村桂子博士 |
三宅龍雄:中村先生のお話を承りまして、目の覚めるような思いをいたしました。特に、科学の場というのは、「ア・プリオリ(生得的)」という言葉がございますが、経験以前の生得的な存在として……。そういう点の捉えかたをされているということがよく解りました。ヒトがこの地球上に現れたときに、既に5,000万種もの生きものがいたのですからね。これはもう、まさに経験以前……。存在そのものが先にあるんでございますから……。
一方、例えば、宗教の側から申しますと、明治時代の真宗大谷派の学者で清沢満之という人は、「生のみが我らにあらず、死もまた我らなり。我らは生死を共有するものなり」と言われました。私は金光教でございますから、清沢満之の言葉の意味を間違って理解しているかもしれませんが、私が聞かせていただいているところでは、「あるはあるにあらず」と言い切って、一粒の米にも先祖がある。だから、われわれが「今ここにある」と言うことは、単に「今ここにある」ということだけではないんだ。ご先祖様がいらっしゃるからである。生きているものは皆、久遠(くおん)の古(いにしえ)の時に起きた生命の誕生から、「同じ長さのいのちを受けついできた同一線上に立つものである」と説かれたそうですが、これが、中村先生がご講演下さったお話と対比できるように思います。
それでは、「宗教と科学の違いがどこにあるか」というと、宗教には、「経験」ということが籠っているんです。その点で「科学と宗教との間に差がある」ということを私は思いました。どうぞ、ご論評くださいませ。
中村桂子:三宅先生のおっしゃろうとされることの意味は解ります。私は宗教のことはよく知らないのですが、確かにそういう認識の差みたいなものはありますね。私はこの講演の最初に「宗教と科学の間の心は同じだ。私の知りたいことは、皆様がご関心あられることとたぶん同じことですが、方法が違う」と申しましたけれども、やっぱり「それぞれ違うんだ」ということは、おっしゃられたことで、よく解りました。
三宅善信:他にございませんでしょうか? では、どうぞ。
三阪和弘:私は、宗教的に立正佼成会という仏教系の教団に所属していますが、本来の所属は神戸大学にあります。中村先生のご意見をお聞きしたいのですけれども、「遺伝子組み換え」という話を最近よく耳にしますよね。「遺伝子組み換え食品」とか、そういうものと生命倫理について、遺伝子の研究をなさっているお立場から、どういうようなご意見をお持ちなのか? というところをお聞かせください。
中村桂子: 「遺伝子を組み換える」ということは、どういうことかと申しますと、遺伝子というものは、先ほどから申し上げているとおり、ひとつの紐のようなものです。この中にゲノムというものがあり、「この部分がこういう遺伝子なんだ」というふうにして、ずっと繋がって、ひとつひとつがそれぞれの働きをしています。例えば、ある遺伝子が、膵臓が出すホルモンの一種のインシュリンを作る役割をしているとしますと、この遺伝子がうまく働かないという場合には、インシュリンがうまく作れないということが起きて、別に食べ過ぎなくても、糖尿病になってしまうという形になっているわけです。
実は、先ほど「私たちは、父親の精子と母親の卵が合体して生まれて来るんだ」と申しました。その時、どういうふうに遺伝子が働くかということをご説明しようとすれば、とても細かいメカニズムですので、生物学の時間でも、この話をするために2,3時間使いますので、本日はちょっとお話しできませんけれども、結論だけ申し上げますと、父親と母親からそれぞれ半分ずつ遺伝子をもらうことになります。けれども、同じ父母の間から生まれた兄弟でも、みんな違いますよね。全く同じ子どもが産まれることはない。これまたゲノムの凄いところでして、それぞれ「唯一無二」のものを創り出すのです。
ところが、細胞分裂で増えるバクテリアなんかは、同じものがどんどん生まれます。この親と同じものが生まれることをクローンと申しますけれども、バクテリアなんかは全部、基本的にはクローンですね。でも、それじゃ多様性が出ない。生きものにとってのひとつの大事なことは、どうして40億年もの長い歳月にわたって続いてこられたかと言えば、多様に、多様にしてきたから続いてこられたんですね。
ですから、生きものの内容を見ていると、とにかく「多様にしよう。多様にしよう」となっているんです。最初はみんなバクテリアのようなクローン――これを無性生殖と言います――だったんですけれども、「これじゃだめだよ」というので、何をしたかといいますと、私たちのようなタイプの生きものを創り出したのです。生物でいえばオス・メス、人間でいえば男女がいるという有性生殖という方法をあみ出しました。私たちの身の回りにいるたいていの生きものは有性生殖になっています。しかし、もともとは、先ほどの『生命誌絵巻』の扇の要に近いほうは、全部無性生殖だったわけです。ところが、途中から有性生殖になって、こんなに多様になるというメカニズムを手に入れました。その結果、有性生殖によって生まれた生きものたちは、どれひとつ取っても、それぞれひとつひとつ違う、唯一無二の存在として生まれるというふうになりました。
それをやるためには何が必要かというと、無性生殖と同じ、単にDNAのコピーだけをやっていたのでは、そんなことは起きませんから、途中で遺伝子を組み換えることによって、いろいろな新しい組み合わせを作ってきた。先ほど「人間は3万から4万の遺伝子を持っている」と申しましたが、たったこれだけの遺伝子の組み合わせで、たとえ人類が60億人いようが、ひとりひとり別の人間が生まれてくるようになっているんです。人類が500万年前に原人として生まれて以来、ずっと人類は続いてきましたし、これからも続いていきます。
今、60億のヒトがいますが、これが、たとえ100億になろうと、いつ人間が生まれようとも、たったこれだけの仕組みで唯一無二のものを作っている。それをやるためには、決まった者同士で遺伝子を交替してたのではダメなので、これをいろいろ組み換えることによって様々な新しいものが生まれる。ですから、「遺伝子組み換え」という事実は、これはもう、生きものにとっては、日常茶飯事に起きている大事なメカニズムなのです。
もし自然界で遺伝子組み換えが起こらないといったら、私たちなんか一人もこの世に存在しません。まず、このことを押さえてから、じゃ、今おっしゃった「遺伝子組み換え作物」というのが、なぜこんなに騒がれているかっていうことですね。それには、まず、「遺伝子組み換え」というものが、実はそういうものなんだということを、皆さんあまりご存知ない。「遺伝子というものは、決まりきったものであって、決して変わっちゃいけないものなんだ」という印象が日本人にはとても強くて、元もといろいろなものを生み出すものなんだというイメージがないものですから、もう「組み換え」というだけで、頭がカッカしてしまう方がいらっしゃいますけれど、これは間違いなんだと……。
じゃ、「遺伝子組み換え作物」はなんで問題になるか? と言えば、今、申し上げた自然界で起きる組み換えは同じ種内で起こる。ヒトはヒト同士、イヌはイヌ同士での組み換えはしょっちゅう行われています。けれども、農作物を作る時に、どんな組み換えをしているかというと、例えば、大豆とか綿とかを裁培している時に病虫害にやられると、たくさん農薬をかけなきゃならない。これにはお金もかかるし、安全性にも問題があるし、環境にも悪影響を与えるというので、大豆の遺伝子の中に、そもそも他の生きものにあった――この場合は地中のバクテリアなんですけれども――その「害虫に強い」という遺伝子を移してやろうという考え方です。組み換えってことは、そもそも遺伝子はできるようになっているのだから、よその生きものから遺伝子を持ってきて、その性質を入れてやる。そうすると病気に強い、害虫に強い作物ができて、それでいいんじゃないかということで、組み換え作物が作られるようになりました。
この場合は、その遺伝子はよそから持ってくるんですね。これは自然界では起きていないことです。ですから、「これはとても大変なことだ」ということで、私たち研究者自身でも――この、よそのものをもってくることができるようになりましたのが、1975年ぐらいですから、まあ30年くらい前の話ですが――1975年のときは、初めての技術で何が起こるか、これをやったら、もしかしたらとんでもないことが起きるのではないか? と研究者自身も思ったのですね。ですから、これはよく注意しなければいけないと思って、研究者は一生懸命チェックもしましたし、30年間この技術を使い続けて――この技術を使っていない研究者はいないといっていいくらい――チェックをしてきました。その結果、「外から遺伝子を持って来るということが、とんでもないことを起こすということはない」ということが判りました。
この理由は、先ほどから私が申し上げていることと関係がございます。さっき、私は、生きものはみんなここ(註=『生命誌絵巻』の扇の要の部分)からスタートしたと言いました。現在、地球には、5,000万種もの生きものがいますが、みんなここ(要)からスタートしている。さっきはキノコとヒトでお話ししました。キノコもヒトもこの辺までは一緒にきて、この辺からみんな分かれていった。
そうしますと、例えば、「害虫に強い」というような遺伝子は、全部の生きものが持っているというわけではないので、どんな生きものでも持っているような遺伝子、例えば「砂糖(グルコース)を分解する」という能力を持っている遺伝子について考えてみます。そうすると、「砂糖を分解する」ってことは何かというと、砂糖を分解するとそこからエネルギーが出てきます。疲れたときは飴を舐める。マラソン選手は糖分が入ったドリンクを飲むというのは、砂糖がエネルギーの素だから。グルコースを分解してエネルギーを摂るということは、あらゆる生きものがやっています。アリもイヌも砂糖を分解しています。
そうしますと、人間の私たちが持っているグルコースを分解するために働いている遺伝子、アリが持っているグルコースを分解するための遺伝子、バクテリアが持っているグルコースを分解する遺伝子、これらを取り出してきて比べることはできます。すると、これが全く同じなのです。ということは何かと言ったら、バクテリアは五千個くらいの遺伝子を持っていますけれども、こういう遺伝子とこういう遺伝子を組み合わせてバクテリアになっている。
人間は3万個の遺伝子を持っているといいましたが、その3万の中に他にも、バクテリアとそっくり同じものがあります。「チンパンジーと比べれば、ほとんど同じ(99パーセント同じ)」と私、先ほど申しました。そういうふうに、生物はみんな仲間なんですから、持ってる遺伝子は基本的には同じだってことが判ったんです。ですから、他種のものを持ち込むからといっても「とんでもないことだ」というわけではない。ということが30年間の研究で判ってきたのです。
じゃ、遺伝子を組み入れた作物はなんでもないかといいますと、これはチェックをしなければならないということがあります。ひとつは、その作物には元もとなかった遺伝子を外から入れたわけですから、その遺伝子が働いた時に、それを私たちが食べたときに毒性を持つとか、病気を引き起こすようなものを作ることはないだろうかという、安全性のチェックはしなければならない。ですから、何にもしていない大豆と、遺伝子組み換えをした大豆を全部分析して、違う成分はないだろうか? 危ない成分はないだろうか? ということを厳重にチェックしなければなりません。それは、もちろんやってます。そんなこともやらないで、みんなが食べた食品に毒が入っていたらとんでもないことですからね。普通の大豆と遺伝子を組み換えた大豆をチェックして、同じか違うかをずいぶんとチェックしています。
そして、2番目が生態系のチェックですね。その大豆を植えたために、そこらへんの生態系が乱れないか? その問題は、「組み換え作物」よりも、もっといろいろなことが起きていますね。ブラックバスとかのケースを見れば、組み換えなんかなんにもしていないですけれど、日本の生態系に従来はなかった違うものを入れた結果、とんでもないことが起こったことは、ブラックバス、セイタカアワダチソウをみても判ります。しかしながら、最初の頃、私は日本中セイタカアワダチソウに覆われてしまうのではないかと心配しましたが、今になってみると、あるところで落ち着いている。だから、生態系っていうのは、一種のものだけががんばるっていうものではなく、やっぱり全体のバランスでできているのだなと思いますけれども……。それにしても、勝手に違うものを入れるというのはまずい。
これはもう、遺伝子組み換えしているか、していないかということとは無関係に、生態系のバランスというのは、私たち人間が勝手に操れるほど解明しているわけではありませんから、この生態系をどうするかということをチェックしなければならない。ですから、そこの畑に遺伝子組み換えを行った新しい作物を作った時に、その作物が周りに影響しないか、そういうこともチェックします。
このふたつをチェックした上で、遺伝子組み換え作物を使っていますので、そこそこ安全かと思いますが、だからと言って、生きものに関しては、さっき申し上げましたように、私たち人間は、名前すら全体の3パーセントしか知らないわけですから、個々の実物については、私たちの知識は頼りないところがあります。私たちはかなり研究しましたけれども、「何をしても良い」とは、私はここでは、絶対に申しません。科学には「絶対大丈夫」とか、そういう絶対という言葉はございませんので、そうは申しません。けれども、「遺伝子組み換え」ということ自身が、本質的にとんでもないことなのではない。これは、自然状態でも遺伝子の中で起きているのですから……。しかし、人工的にやるからには、こういうことを守っていかなければならない。こうやって、使っていくのが遺伝子組み換え作物だと私は思います。
ただ、今やたらに問題になっていますのは、これは「安全性の問題」ではないんです。農業戦略なのです。アメリカの会社が主としてこういうことをやってますので、この技術(特許)で「アメリカが世界を席捲する」と、ヨーロッパなどではたいへん困っています。アメリカの会社が作っている大豆やらいろんな農作物の研究のスタートは1980年頃です。1975年にこの技術が確立しましたから、1980年頃に、実用化への研究をスタートさせました。それが、今、商品になっているわけです。1980年頃は、日本でも「バイオテクノロジーブーム」と新聞なんかにもよく載りました。日本の会社も鉄鋼会社から出版社に至るまで、「うちはバイオテクノロジーをやります」とおっしゃった時期なんです。
けれども、そんなこと言うだけでできるような柔な技術ではありません。「5年で儲(もう)かる」などという性格の技術ではありません。ですから、きちっと研究していかなければ成果が出ないので、日本では、全部の会社が途中で止めてしまいました。ところが、今、バイオ技術を売っている一番大きな会社はモンサントという会社ですが、この会社は1980年代から現在まで、実をいうと、長い間、儲かりませんでしたから、苦しくて、ある時、潰れかけました。けれども、これを「大事な技術だから」といって続けてきたんですね。だから、独占しちゃった。私は、農業をひとつの企業に独占されるのは望ましくないことだと思います。
けれども、そういう状態にしてしまったのは、もし、日本もきちっと新技術の開発に取り組んでコンペティティブ(競争的)になっていれば、一番いいものをどこか1社が独占するなんてことがなくやれたと思いますが、「それができなかったじゃないか」という気持ちが、日本の研究者の心の中にはあった。なぜこの人たちが独占したのかっていうのをよく考えてほしい。そして、もうひとつは、ここでバイオ技術を企業化していますね。そうすると、明らかにこれは経済の問題です。しかし、農業は経済原理だけで行ってはいけないと、私は思っています。
ですから、このせっかく作った「遺伝子組み換え」作物という技術を上手に使っていかなければなりませんけれども、そのために、世界全体、特に日本が、農業というものをきちっと考えて、どういう農業をするべきか……。日本はこんな素晴らしい気候の中で、世界最低の食糧自給率という農業をやっている国であることが、私は許せないと思っています。農業というものが、もっと環境のことを考え、安全性のことも考え、それから、美味しさも考え、きちんとした農業をやって、農業に携わる人の生活のことも考えて、農業政策をきちっとやった上で、遺伝子組み換え作物を作る。環境によい、安全でなるべく安く作るために、組み換え作物を作るのなら、私は使っていくことができると思っています。このように、あまりにも周りの状況が複雑すぎて、単純にイエス・ノーがとても言いにくい、というのが本音です。
三宅善信:ありがとうございます。本当にひとことで言いにくい問題を、判り易く教えていただきました。われわれ大阪国際宗教同志会も、ある意味で、仏教は仏教、神道は神道、キリスト教はキリスト教というような、いわば歴史的な遺伝子を持っている訳ですけれども、どんどんとそれを組み換え、シャッフルしていって、さらに、お互いに学び合うということをさせていただいています。儒教のほうでは「身体髪膚(しんたいはっぷ)これを父母に受く」という言葉がございますが、本日、この会場には、私の父も母も兄も来ておりますが、確かに同じ遺伝子を受けついでいるはずなのに、兄弟で見た目もずいぶんと違う。ということが「なるほどそうやねんな」ということを、実感させていただいたわけでございます。
本日は、お忙しい中、中村先生に貴重なお話を聞かせていただき、ぜひとも私共ももう少し勉強させていただいて、本当言うと、もっと深いところに重大な問題があるのかもしれません。そこまで聞かせていただくために、われわれ宗教家ももっと勉強させていただかないといけないなと思います。
お約束の時間がまいりましたので、これで質疑応答を終わらせていただきたいと思います。どうぞ、もう一度先生に拍手をお願いします。
(連載おわり 文責編集部)