レルネット主幹 三宅善信 ▼七夕(たなばた)はお盆の行事 8月は鎮魂の月である。太平洋戦争関係の6日と9日の広島・長崎の原爆忌や15日の終戦記念日はいうまでもなく、12日の日航ジャンボ機墜落事故慰霊祭をはじめ、13日から16日にかけて各地で行われるのお盆の行事から、甲子園の高校野球にいたるまで、すべてが死者に対する鎮魂の行事なのである。では、いったい8月の正体って何なのだろう? 8月の和風名は、葉月である。この「はづき」という名の由来にはいくつかの説がある。まず、木の葉が黄葉して落ちる月、つまり葉落月がなまったものであるという説。この月に初めて雁が飛んでくるので「初来(はつき)月」であるとする説。また、稲の穂が張ってくる月なので「穂張(ほはり)月」というのを「はづき」と略したともいわれる。しかし、これは、いわゆる「旧暦(太陰太陽暦)」のことであり、現在(新暦=グレゴリオ暦)の季節では、だいたい9月頃のことである。むしろ、本エッセイの主旨(8月は鎮魂の月)からすると、「葬(はふ)り月」の省略形だと解釈したほうがいいくらいだ。 私は、前回の作品(遊牧民と農耕民の結婚:モンゴル訪問記)にいおいて、七夕(たなばた)祭について書いたが、モンゴルで牽牛・織女を見ることができなかった悔しさからではないが、後で、本来の七夕祭は7月7日(新暦)ではないことにい気がついた。新暦の7月7日だと、まだ、梅雨の真っ最中で、星空が仰げない日が多いし、旧暦の7日の月齢は必ず「上弦の月」になるが、月の満ち欠けに関係ない新暦の7日だと、場合によっては「望(満)月」に当たることもあって、明るすぎて必ずしも星空がよく見えるとは限らないのだ。したがって、本来、「七夕」祭は旧暦で行われるべき習俗である。そういえば、有名な仙台の「七夕」祭は、「月遅れ」の8月7日を中心に行われる。それどころか、同じく、東北三大祭りの青森の「ねぶた」祭や秋田の「竿灯」祭も、どうやら「七夕」祭の変形と考えてよさそうだ。
「七夕」祭は全国で行われるが、仙台の「七夕」は特に豪華絢爛である。昔の農村ではナマカビといい、祖先の墓を掃除し、市中ではこの夜から盆提灯に燈をともす。農家では七夕は田の神をお迎えする日として新藁(わら)や真菰(まこも)で馬を作って屋根の上に載せて、この夜は外出しなかった習わしがあった。「七夕」はお盆前の先祖を迎えるための禊(みそぎ)の意味もあるので、お盆の日付に連動するほうが妥当である。 ▼お盆は、儒教や神道の風習! 「お盆」の正式名称は「盂蘭盆会(うらぼんえ)」である。盂蘭盆とは、サンスクリット語の「ullambana(ウラバンナ)」を音訳したもので、「(先祖や関係者が地獄や餓鬼道に落ちて)逆さづりにされ(苦しんでいる)」という意味で、そのために供養を営むのが盂蘭盆会である。もっとも、この行事自体は、輪廻転生(たとえ身内であっても、転生したら別人格の他者になる)を説くインド的考え方ではなくて、先祖を祀ることを重視する中国(儒教)的な発想である。あるいは、もっと踏み込んで、神道の風習であるといってもよい。仏典に『盂蘭盆経』というのがあるが、これなど、後代に中国で創作された「偽経」である。 「主幹の主観」の読者ならご存知だと思うが、一応、念のために紹介する。お釈迦様の弟子の一人、目連尊者という人が、神通力で亡き母の姿を見たところ、母親は餓鬼道に落ちて苦しんでいた。「何とかして救いたい」と、釈尊に尋ねると、「7月15日に、過去7世の亡き先祖や父母たちのために、ご馳走を作り、僧侶たちに与え、その飲食をもって、供養するように」と教えられた(僧侶に都合のよい話だ)。教えの通りにすると、目連の母親は餓鬼道の苦を逃れ、無事成仏することができた(釈迦自身といえども、執着があっては解脱できないはずなのに、極めて中国的なご都合主義と化している)そうだ。この故事が盂蘭盆会の始まりといわれている。 東京あたりでは、7月15日(新暦)を中心に、13日を「迎え盆」、16日を「送り盆」といい、13日から16日までの4日間を「お盆」の期間としているそうだが――そういえば、お中元も、まず東京の関係者から届き、半月ほどしてから関西の知り合いから届く――わが大阪をはじめ全国各地とも、こと「お盆」に関しては、圧倒的に旧暦の7月15日もしくは、その便宜上の変形である新暦の8月15日を中心に「月遅れのお盆」が行われている。この現象は、「正月」をはじめ数々の伝統的な節句や民俗習慣が、なんでもかんでも「文明開化」の名の下に欧米化を進め、何の関連もない新暦(グレゴリオ暦)で実施されるようになった明治期以後――今でも、中国や韓国その他の東南アジア各国の「正月(春節)」はすべて旧暦で行われている――の日本にあって、奇跡的にも旧暦の側が優勢な民俗習慣である。 お盆には、先祖や亡くなった人たちの精霊(アニミズムの世界)が燈明を頼りに帰ってくるといわれ、13日の夕刻に、仏壇や精霊棚(しょうりょうだな)の前に盆提灯や盆灯籠を燈し、庭先や門口で迎え火として麻幹(おがら=芋殻)を焚く。それが「迎え火」である。盆提灯をお墓で燈し、そこでつけた明かりを持って精霊を自宅まで導くという風習もあり、これを「迎え盆」ともいう。これは、まるで、日頃からその辺(雲の中や草場の影)をウロウロしていた先祖の霊魂が、夜間の航空機がビーコン(誘導電波)と滑走路に点された誘導灯を目安に着陸してくるのと同様のシステムである。それぞれの「家」毎にビーコン(鐘やご詠歌)や誘導灯(迎え火)を設け、先祖の霊魂を家の中まで招き入れるのである。 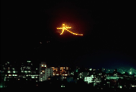 14・15両日は、精霊は家に留まり、16日の夜、家を去り、元いたところに帰ってゆく。伝統的な日本の霊魂観では、先祖の霊魂は、決してキリスト教で説くような天国や西方十万億土の浄土といった観念的な世界ではなく、われわれの住むこの世界の中に同居して(草場の影から見守って)いるのである。さもなければ、せっかく極楽に往生した先祖がなんで好んでこの娑婆に戻ってこなければならないのだ。自分の「遺体(遺伝子を受け継ぐものとしての遺した身体)」としての子孫の無事安泰を確認(そのために、われわれは先祖の霊魂を接待する)したら、満足した先祖の霊魂を送り出すために迎え火と同じところに、今度は送り火を焚き、帰り道を照らして、霊を送り出す。これを「送り火」といい、最も有名なのは、京都に五山に炎で文字が浮かび上がる「大文字焼き」の送り火である。 14・15両日は、精霊は家に留まり、16日の夜、家を去り、元いたところに帰ってゆく。伝統的な日本の霊魂観では、先祖の霊魂は、決してキリスト教で説くような天国や西方十万億土の浄土といった観念的な世界ではなく、われわれの住むこの世界の中に同居して(草場の影から見守って)いるのである。さもなければ、せっかく極楽に往生した先祖がなんで好んでこの娑婆に戻ってこなければならないのだ。自分の「遺体(遺伝子を受け継ぐものとしての遺した身体)」としての子孫の無事安泰を確認(そのために、われわれは先祖の霊魂を接待する)したら、満足した先祖の霊魂を送り出すために迎え火と同じところに、今度は送り火を焚き、帰り道を照らして、霊を送り出す。これを「送り火」といい、最も有名なのは、京都に五山に炎で文字が浮かび上がる「大文字焼き」の送り火である。▼甲子園の球児は、なぜ純情でなければならないのか? 本文の冒頭で述べた広島・長崎の原爆忌や終戦記念日が鎮魂慰霊の日であることはいうまでもないが、なぜ、甲子園の高校野球までが鎮魂の行事なのであろうか? 私が、若い頃から不思議であったことのひとつに、高校球児の演出された「純情性」があった。同じ高校生のスポーツといっても、サッカー選手なら長髪も茶髪もやりたい放題なのに、どういう理由か、高校球児だけが未だに坊主頭である。同じ現代っ子の高校生なのに、野球もサッカーも全国レベルの帝京高校など、サッカー部と野球部とでは同じ学校とは思えないくらいの違いがあるでないか…。 それに、高野連(高等学校野球連盟)のアナクロニックな態度も解せない。当の野球部員が不祥事を起こしたのならいざ知らず、同じ学校の生徒が起こした不祥事ですら、連帯責任で「出場辞退」を「強要」してくる。今時の高校生なら、暴力事件どころか援助交際をしている女子高生などいくらでもいるはずだし、当の野球部員だって、アイドル的なスター選手はなど、する気になれば不純異性交遊だっていくらでもしているはずだ。しかし、こと高校野球に関しては、そのような「不祥事」は一切御法度だし、高野連からの「勅命」には、皆、低頭して聞き入れている。これを見て、戦前の軍隊を連想してしまうのは、私だけであろうか? こんな時代錯誤が未だに通用している(どころか、拡大再生産されている)原因はどこにあるのだろうか? 高校球児の純情が創られた純情であることは、甲子園大会のわずか3カ月後にあるプロ野球のドラフト指名の時に、同じ高校生が億単位の契約金をちゃっかり請求することからしても明らかである。しからば、なぜ、夏の全国高校野球選手権大会だけは「別格」なのであろうか? なぜ、各都道府県から1校づつしか出場できない(東京都と北海道のみ2校)のだろうか? 府県によっては、学校の数は10倍以上違うであろう。それに、過去何年間かのデータをとれば、何十年も優賞校を出していない弱小県もあれば、毎年のように上位校を輩出する強豪県もあるであろう。これでは悪平等というものだ。同じ高校野球でも、春の「選抜」大会では、大阪などの強い府県は2〜3校出場できるが、逆に弱い県は出場できない県もある。これこそ、日夜練習に励んでいる選手の実態を反映しているはずである。 これらの問いを一挙に解決する答えがある。それが、「夏の高校野球は、単なるスポーツ大会にあらずして、鎮魂の現代的儀礼である」という結論である。この大会が、お盆の時期に行われるのもそのためだ。戦前から続く(戦前は全国中等学校野球大会)この大会は、多くの才能のある球児たちを戦地へと輩出した。その中には、太平洋戦争の藻屑と散った若者も数多く含まれていたに違いない。あの開会式の入場行進の様子はどう見ても、学徒出陣を彷彿させるし、あの訳の判らない選手宣誓も軍隊を想起してしまう。何よりも、8月15日の正午には、プレーを中断して、サイレンの音と共に1分間の黙祷が行われるではないか…。終戦から54年が経過した現在、日本国中で、この日、この時間帯に「黙祷」をしているところといったら、一部の宗教団体を除けば、天皇皇后両陛下もご臨席される日本武道館の政府主催の戦没者慰霊式典と甲子園の高校野球くらいのものである。そう、夏の甲子園は、鎮魂の儀礼なのである。したがって、不祥事は御法度なのであり、全国一律の出場枠なのである。かつての帝国陸軍の徴兵制が県単位で行われたことと見事に符合している。 ▼墜落事故に見る遺体へのこだわり 最後に、12日の日航機墜落事故の話である。この日航機墜落事故とは、いうまでもなく、1985年8月12日の夕方におきた日本航空ジャンボ機墜落事故のことである。14年も前のことなので若い読者の方でご存知ない方があるかもしれないので、概略すると、羽田発大阪行き日本航空123便ボーイング747SR型機が、機体後部の圧力隔壁を破損したことによって垂直尾翼が大破し、30分にも及ぶ迷走飛行の末、群馬県上野村の御巣鷹山の尾根に墜落。乗務員15名、乗客509名、計524名のうち、女性4名を除く520名が死亡した。単独機としては世界の航空史上最悪の事故となった。 実は、私は、この飛行機に乗っていたかもしれないのである。当時、ハーバード大学世界宗教研究所での学究生活を終えた私は、日本に帰る便を探していた。帰国するといっても、一旦、大阪に戻ってしまえば、また忙しい日々に突入しなければならないので、当時、つくばで開催されていた科学万博を見物し、友達と東京方面を少し彷徨いてから大阪に戻ろうと思い、ボストンから大阪へ直行せずに、まず、成田へ帰国し、東京で遊んでから何喰わぬ顔で、羽田から伊丹への便(123便)に乗って大阪へ戻ろうと考えていたのである。そうすると、伊丹(大阪国際空港)への到着時刻は、ほとんどアメリカからの到着便と同じ頃になる。事実、そうしたが、いろんな都合で、数日、日程が遅れてしまい、この事故の発生を米国を出発する間際に聞いた。なにせ、この事故で死亡した乗客の中には、アメリカで最も有名な日本人歌手であった坂本九さんも含まれていたから、米国でも大きく採り上げられた。 この航空機事故の際に、日本と欧米各国(あるいはインドやアラブなどそれ以外の地域も同様かもしれない)との事故に対する対応の違いを見た。外国では、航空機事故が発生すると、遺体の収容もさることながら、一番関心を持たれるのは、事故の原因究明である。もちろん、生存者があると考えられるような場合であれば、徹底的に捜索活動が行われるであろうが、誰の目にも生存者の発見どころか遺体の識別すら不可能であるというような状況なら、日本のごとく、徹底した遺体捜査と身元確認など行わない。それよりも、保険金の請求や慰謝料の交渉などの具体的な案件がどんどんと進む。ところが、日本では、手だけや片足だけといったバラバラになってしまった身体の一部に関しても、徹底的に誰のものかの確認作業が行われた。その作業は、なんと127日間にわたって行われた。その間、季節は夏から冬にすっかり変わってしまったぐらいだ。日本人のこれらのこだわりについては、運悪くこの機に乗り合わせた外国人の遺族も驚いたような口調で証言している。 彼らにとっては「Death is death(死は死)」であって、死者の遺体よりも、(死によって肉体と分離した)魂の平安が問題なのである。しかしながら、日本人にとっては、近しい人の「死」を確認するためにはどうしても状況証拠だけでは不十分で、「遺体」という物証が必要なのである。一片の「戦死通知」だけでは、不十分(年金の請求など、法的には完全に有効)で、戦後、半世紀以上を経過した今年も、沖縄や南太平洋の島々には、多くの遺骨収集団が派遣され、慰霊祭が行われていることから見ても明らかだ。 これだけほとんど行事が新暦で行われるようになった現代でも、こと鎮魂・慰霊に関する行事は、日本人の性格からして8月に行われるのが望ましいのである。そう、8月は文字通り「葬(はふ)り月」なのだ。 |
|||||

